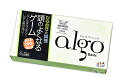「集中力が続かない」「興味がコロコロ変わる」「自分から学ぼうとしない」——そんなお悩みを感じていませんか?
忙しいお父さん・お母さんにとって、日々の子育てはトライ&エラーの連続です。頑張って声をかけても、うまくいかない日もある。そんな時こそ、子どもの「自ら学ぶ力」を育てるヒントがほしくなりますよね。
実は、今世界中で注目されている「レッジョ・エミリア教育」は、まさにその“主体的に学ぶ力”を育てる教育法。お子さんが持つ「100の表現の力(100 languages)」を信じ、それぞれの個性を尊重しながら、学びへの意欲を引き出すアプローチです。
この記事では、幼児教育の知見をもとに、レッジョ・エミリア教育の考え方や家庭での実践方法、そしてお子さんにどんな変化が生まれるのかを、やさしく解説していきます。
レッジョ・エミリア教育とは?その基本理念をやさしく解説
イタリア発、“子どもは100の言葉を持つ”という思想
レッジョ・エミリア教育は、イタリア北部の小さな町「レッジョ・エミリア」で生まれました。第二次世界大戦後、町の再建を目指す人々が「子どもたちの力を信じよう」という思いから始めた教育運動です。
この教育の中心には、「子どもは100の言葉を持つ」という考え方があります。ここでいう“言葉”とは、話すことだけでなく、絵を描く・歌う・体を動かす・物を作るなど、子どもが世界を理解し表現するすべての方法を指します。
つまり、子どもたちは一人ひとりが「自分の世界を表す力」を持っており、その表現の仕方に優劣はない——それがこの教育の根底にあります。
教師・親・子どもが「共に学ぶ」姿勢
レッジョ・エミリア教育では、大人が「教える人」ではなく「一緒に学ぶ仲間」として関わります。
たとえば、お子さんが道端の石を拾って「これ、なんで丸いの?」と聞いたとき、
「丸いから転がるんだね」と答えるのではなく、
「どうしてだと思う?」と問い返して一緒に考える。
そのプロセスの中で、子どもは考える力・仮説を立てる力・他者の意見を聞く力を育てていきます。
こうした“対話の積み重ね”が、子どもの思考を深め、主体的な学びにつながるのです。
環境は「第3の教師」
レッジョ・エミリア教育では、「子ども」「教師」に加えて、“環境”が第3の教師とされています。
たとえば、光が差し込む窓辺、素材が整然と並ぶ棚、描いた絵が飾られた壁——それらはすべて子どもの創造性を刺激し、探究心を引き出す“教育的な空間”です。
家庭でもこの考え方を取り入れることができます。
例えば、リビングにお気に入りの画用紙とクレヨンを置く。お散歩で拾った木の実を並べて観察する。そんな「子どもが手を伸ばしたくなる環境」をつくるだけで、学びの姿勢が変わっていきます。
なぜ今、レッジョ・エミリア教育が注目されているのか
「受け身の学び」から「主体的な学び」へ
近年、日本でも「非認知能力」や「探究学習」が注目されています。これは、単に知識を詰め込むのではなく、自分で考え・行動し・学び続ける力を重視する教育観です。
レッジョ・エミリア教育は、まさにその考え方と一致しています。
お子さんが「これやってみたい!」と自ら動き出す瞬間、その興味の火を消さずに見守ること。失敗しても「どうしてうまくいかなかったのかな?」と一緒に考えること。そうした積み重ねが、学ぶ喜びと自信を育てていきます。
データで見る“探究する子どもの育ち”
OECD(経済協力開発機構)の調査では、幼児期に自ら考え行動する体験を重ねた子どもほど、学齢期以降の学習意欲・社会性が高いことが報告されています。
これは、単に「勉強ができるようになる」ではなく、自分の考えを持ち、人と協力しながら課題を解決する力を意味します。
つまり、レッジョ・エミリア教育のような探究型の学びは、お子さんの“未来を生き抜く力”を育てる土台になるのです。
家庭でできるレッジョ・エミリア的な環境づくり
“失敗しても大丈夫”と思える安心感をつくる
レッジョ・エミリア教育の根底には、「子どもは有能な存在である」という信念があります。
つまり、お子さんは自分の力で考え、試行錯誤することができる存在だということ。
そのために家庭で大切なのは、「間違っても大丈夫」「やり直せるよ」という空気をつくることです。
たとえば、工作で紙を切りすぎてしまったときに「もう一回やってみようか」と声をかけるだけで、子どもは“失敗=悪いことではない”と学びます。
こうした経験が、「挑戦する姿勢」や「粘り強さ」といった非認知能力を育ちを支える大切な土台になります。
親御さんにとっても、完璧を求めず“見守る勇気”を持つことがポイントです。
子どものペースを尊重することで、安心して自分を表現できる家庭の空気が生まれます。
遊びを通して「探究する姿勢」を引き出す
レッジョ・エミリア教育では、“遊び=学び”という考え方が根付いています。
子どもは遊びながら観察し、考え、工夫し、結果を見て学んでいく。
この過程そのものが「探究」です。
たとえば、お子さんがペットボトルに水を入れて「音が違う!」と気づいたとき。
「どうしてかな?」と一緒に考えるだけで立派な探究活動になります。
正解を教えるよりも、子どもの気づきを深める質問を投げかけてみましょう。
「なんで音が変わったと思う?」「ほかのものでも試してみようか?」
——この一言が、子どもの思考をぐっと広げます。
“環境”が学びを変える
家庭での環境づくりといっても、大げさな準備は必要ありません。
たとえばこんな工夫が、お子さんの学びを自然に引き出します。
壁にお絵かき作品を貼る(自分の表現を誇りに思える)
リビングに「創作コーナー」をつくる(すぐに描ける・作れる)
自然素材(木の実・葉っぱ・石など)を置いておく(観察や分類のきっかけに)
絵本や図鑑を取り出しやすく並べる(興味に合わせて調べられる)
大切なのは、子どもが主体的に手を伸ばせる距離に“学びの素材”を置くことです。
そうすることで、家庭そのものが「第3の教師」としてお子さんの育ちを支える空間になります。
子どもが変わる!レッジョ・エミリア教育の効果
自分で考える力・表現する力が育つ
お子さんが自ら問いを立て、考え、試すプロセスを重ねることで、「思考する力」と「表現する力」がバランスよく育っていきます。
レッジョ・エミリア教育では、作品づくりを通して自分の考えを“見える形”にすることを大切にしています。
たとえば、粘土で「今日の気持ち」を形にする、色で「音」を表すなど。
答えのない世界に自分なりの意味を見出す体験が、創造力の基礎になります。
コミュニケーション能力と共感力が伸びる
子どもたちは、同じテーマでも違う視点を持っています。
「海って青いよね」「でもオレンジにも見える」といったやり取りの中で、互いの感じ方を知り、考えを尊重する力が育ちます。
家庭でも、「どうしてそう思ったの?」と問いかけたり、「○○くんはこう思うんだね」と共感を言葉にするだけで、お子さんの“聞く力”と“伝える力”を伸ばせます。
レッジョ・エミリア教育は、単に知識を増やす教育ではなく、人と関わりながら学ぶ力を伸ばす教育でもあるのです。
失敗を恐れず挑戦する心が育つ
「うまくいかなくても大丈夫」と思える環境の中で育った子どもは、失敗を前向きに受け止められるようになります。
「やり直す力」や「自分で考える習慣」は、受験や将来の仕事にもつながる“生きる力”です。
たとえば、家庭で「挑戦のノート」をつくって、できたこと・できなかったことを一緒に書き出してみるのもおすすめです。
「昨日よりちょっとできたね」という積み重ねが、お子さんの自信を支えていきます。
学びが「楽しい!」に変わる
レッジョ・エミリア教育では、「興味から始まる学び」を何より大切にします。
お子さんが“自分で見つけたテーマ”に夢中になる時間は、まさに集中力と創造力の宝庫です。
家庭でも、親御さんが「なんでそれが好きなの?」と興味を寄せて聞くことで、お子さんの中の“学びのスイッチ”が入ります。
学ぶことが楽しいと感じられれば、自然と挑戦する姿勢も育っていきます。
家庭で実践するためのヒント:知育玩具の活用法
「遊び=学び」を体験できる知育玩具とは
レッジョ・エミリア教育では、子どもの“探究心”を育てることが中心にあります。
家庭でその学びを支えるとき、役立つのが「知育玩具」です。
知育玩具というと、「学習目的の道具」と考えられがちですが、レッジョ・エミリアの視点では少し違います。
おもちゃは“教えるため”のものではなく、**子ども自身が試行錯誤できる“素材”**です。
つまり、正解が一つに決まっていないものほど、子どもの創造力や集中力を引き出します。
たとえば、積み木・ブロック・色タイルなどの組み合わせ遊びは、形やバランスを考える力を育てるのに最適です。
「高く積むにはどうすればいい?」と考えることで、自然と観察・予測・実験の姿勢が生まれます。
この過程こそが、家庭での探究的な学びです。
創造力を引き出すアイテムの選び方
知育玩具を選ぶときのポイントは、**「子どもの自由な発想を広げられるか」**という視点です。
派手な音や光で一方的に刺激を与えるおもちゃより、手を動かして形を変えたり、試したりできる玩具の方が、探究の力を育てます。
たとえば、
色や形が異なるブロックで構成を考える(空間認識力)
磁石やギアを組み合わせて動かす(論理的思考)
粘土や工作キットで形づくる(表現力・感性)
このような遊びの中で、お子さんは“やってみる → 失敗する → もう一度やる”というサイクルを繰り返しながら、考える力を伸ばしていきます。
親御さんは「上手にできたね」よりも「どうやって作ったの?」「ここを変えたんだね」とプロセスを認める声かけを意識してみてください。
それが「自分の考えを大切にしてもいい」と思える安心につながります。
年齢別におすすめの知育玩具
3〜5歳ごろ:感覚を刺激するシンプルな素材
→ 木製ブロック、色つきキューブ、積み木、型はめパズルなど
この時期は手触り・形・重さなど、感覚的な学びを通して世界を理解していく時期。6〜8歳ごろ:考える力・構成する力を育てる
→ 磁石ブロック、ギアパズル、構造系ブロックなど
試行錯誤を通して「こうしたら動く」「倒れないようにするには?」と考える力が育ちます。9歳以降:創造・論理・表現の段階へ
→ プログラミング系、科学実験セット、アート・クラフト玩具など
想像を形にしながら「思考の筋道を立てる」練習ができる時期です。
お子さんの興味や発達段階に合った玩具を選ぶことが、学びのモチベーションを高めます。
親子で「学びを共有する時間」をつくる
知育玩具を使う時間は、“一緒に学ぶ時間”に変えることができます。
お父さん・お母さんが「こうしたらどうなるかな?」と一緒に考えることで、子どもの学びが深まります。
遊びの途中でうまくいかなかったときも、「なんで倒れたんだろうね」「どうしたら崩れにくくなるかな?」と声をかけてみましょう。
そのやりとりの中で、子どもは自分の思考を言葉にし、考えを整理する力を身につけます。
家庭での遊びが単なる「楽しい時間」ではなく、思考と表現の練習の場になるのです。
家庭で使いたいおすすめの知育玩具
また、知育玩具は“長く遊べるもの”を選ぶのもポイントです。
単なる一時的なブームで終わらず、年齢や発達に応じて遊び方が変化していくものを選びましょう。
1.テンヨー 『脳ブロック』
手のひらサイズから始まる“遊びの旅”。テンヨーの知育ブロックシリーズは、形や色を自分で選びながら創り出す楽しさが詰まっています。小さなお子さんが「やってみたい!」と手を伸ばす瞬間が、集中力や想像力の育ちを後押しします。親御さんも一緒に遊ぶことで、笑顔と達成感を共有できるのも魅力。家庭での遊び時間を、子どもの“育ちを支える”時間に変えてみませんか?
2.カワダ 『ナンスピ』
「遊びながら夢中になれる」その瞬間が、集中力を育てる大切な出発点です。KAWADAのこのボードゲームは、数字カードやライトの順番を記憶してチャレンジする3つのモードを備え、遊びながら集中力・注意力・記憶力を鍛えられます。対象年齢6歳以上、コンパクトなサイズなのでご家庭のリビングでも楽しめ、お子さんと一緒に「できた!」という達成感を分かち合えるのも魅力。家庭時間を、育ちを支える“遊び時間”に変えてみませんか。
3.マテルゲーム ブロックス トライゴン
この知育ボードゲームは、「遊びながら賢くなる」家庭時間を実現します。2〜4人で遊べる仕様で、対象年齢7歳以上。三角形のピースを交互にボードに配置し、最終的に多くのマスを埋められたプレイヤーが勝利というルールで、視覚-空間能力や計画力、集中力を育てる工夫が詰まっています。遊びが終わったら「どこが難しかった?どう変えた?」と話すことで、お子さんの“考える力”を育ちを支える時間にもなります。
4.アルゴ ベーシック (頭のよくなるゲーム)
数学と論理的思考を楽しく伸ばせる一冊です。カードを使って「何が隠れているの?」と推理しながら遊ぶ教材で、遊びの中に集中力や分析力が自然と育まれます。お子さんが「気になる!」「もう一回やってみたい!」という瞬間を増やせるのも魅力。お父さん・お母さんがそばで声をかけながら、「今日の発見はね」と子どもの育ちを支える時間になる一冊です。
よくある質問(Q&A)
Q1:レッジョ・エミリア教育は家庭でもできますか?
はい、十分に可能です。特別な教材や教室がなくても、「子どもの興味を大切にする」「一緒に考える」「環境を整える」という3つの視点を意識すれば、家庭でも自然に取り入れられます。
たとえば、お子さんが夢中になっているテーマ(昆虫・星・料理など)に関連する図鑑や素材を用意して、一緒に観察したり調べたりする。それだけでも立派な“レッジョ的探究”です。
Q2:モンテッソーリ教育と何が違うの?
モンテッソーリ教育は「自立と秩序」を重視し、手先を使った具体的な教具で学びを深めるのが特徴です。
一方、レッジョ・エミリア教育は「創造と対話」を軸に、子どもが自分の世界を表現することを大切にします。
つまり、モンテッソーリは“できるようになる学び”、レッジョは“考えることを楽しむ学び”。
どちらも素晴らしい教育法であり、家庭では組み合わせて取り入れても構いません。
Q3:子どもが好きなことばかりして、勉強しなくなりませんか?
ご安心ください。レッジョ・エミリア教育は、自由放任とは違います。
「子どもが興味を持ったことを入り口に、学びを深める」というのが大切なポイントです。
たとえば、車が好きなお子さんなら、「車の形を描く」「走る距離を測る」「タイヤの回転数を数える」など、学びのテーマはいくつも見つかります。
興味から出発することで、子どもの集中力と理解力はむしろ高まるのです。
注意点とデメリットも知っておこう
大人の“期待”が強すぎると逆効果に
レッジョ・エミリア教育は、子どもが自分のペースで考えることを大切にしています。
そのため、親御さんの「もっとできるはず」「こうしてほしい」という思いが強すぎると、子どもの主体性を奪ってしまうことがあります。
「見守る勇気」を持つことが、実は最も難しく、そして最も大切です。
成果を急がず、プロセスを大切に
探究型の学びは、結果がすぐに見えるものではありません。
「今日作った作品の意味がわからない」と思う日もあるでしょう。
でも、その過程でお子さんがどんな表情をしていたか、どんな言葉を発していたか——そこに成長のサインが隠れています。
“できたこと”よりも“考えていた姿”を見取ることが、親としての学びにもつながります。
親自身も「学び続ける姿」を見せよう
子どもは親の姿をよく見ています。
レッジョ・エミリア教育の根本は、「子どもも大人も共に学ぶ」こと。
お父さん・お母さんが「わからないね」「一緒に調べてみようか」と言える関係こそ、最良の教育環境です。
完璧でなくて大丈夫。“いっしょに育つ家庭”を目指す気持ちが、何よりもお子さんの安心につながります。
まとめ
家庭でもできる、レッジョ・エミリア的な学び
レッジョ・エミリア教育は、特別な施設やカリキュラムがなくても始められます。
家庭の中で「探究」「対話」「表現」を意識するだけで、日常が“学びの場”に変わります。
お子さんの「なぜ?」「やってみたい!」を尊重することが、未来への一歩を支える原動力になります。
これから試してみたい工夫
お子さんの「なんで?」を止めずに、一緒に考える時間をつくる
遊びや知育玩具を“探究の素材”として活用する
失敗を肯定的に受け止める言葉を増やす
家の一角に「創作・実験コーナー」をつくる
親自身も学びを楽しむ姿を見せる
レッジョ・エミリア教育は、子どもだけでなく、親も一緒に成長できる教育法です。
小さな問いかけや、身近な素材のひと工夫からでも始められます。
お子さんが自分の思いを自由に表現し、「考えるって楽しい」と感じられる家庭を、一歩ずつ育てていってほしいなと思います。
おわりに
レッジョ・エミリア教育の魅力は、“子どもを信じるまなざし”にあります。
完璧な方法論よりも、お父さん・お母さんが「あなたの考えを聞かせて」と向き合うこと。
その積み重ねが、どんな教材よりも深い学びを生み出します。
今日の会話の中に、探究の芽があるかもしれません。
お子さんの育ちを支える毎日のひとときを、大切にしてほしいなと思います。