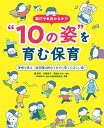教育・保育要領に示される「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」、いわゆる「10の姿」は、保育現場でよく耳にするキーワードです。けれど「実際に日常の保育でどう見取ればよいのか」「記録や要録にどう結びつければいいのか」と悩む保育士さんも少なくありません。
例えば「思いやりのある子」や「協同性」という言葉。大切なのはわかるけれど、子どもたちの小さなやりとりをどう実践につなげればいいのか迷うこともあるでしょう。また、保護者さんに「今日はこんな姿がありました」と伝えるときに、どのように言葉を選べば信頼につながるのか不安に思う声もあります。
この記事では、10の姿を一つひとつ整理し、日常の遊びや生活の中でどのように表れるのかを具体的に紹介します。さらに、職員同士の共有や保護者さんへの説明につなげるヒント、実践を支える書籍の情報まで幅広くお伝えします。読み進めることで「これなら明日からできる」という視点が見つかると思います。
教育・保育要領に示される「10の姿」とは
10の姿が示された背景
2017年の教育・保育要領改訂で、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」が明文化されました。これは、小学校以降につながる学びの基盤を、乳幼児期のうちに整えることを目的としています。従来の「5領域」(健康・人間関係・環境・言葉・表現)をより具体的に子どもの姿として表したものが「10の姿」です。
背景には、学力偏重ではなく「非認知能力」と呼ばれる意欲・協調性・自己肯定感の大切さが注目されてきた流れがあります。数値では測りにくいけれど、生きていくうえで欠かせない力を、どうやって育ちとして見取るかが重視されたのです。
幼児期の終わりまでに育ってほしい力
10の姿は以下のように整理されています。
健康な心と体
自立心
協同性
道徳性・規範意識の芽生え
社会生活との関わり
思考力の芽生え
自然との関わり・生命尊重
数量や図形、文字などへの関心・感覚
言葉による伝え合い
豊かな感性と表現
これらは、園児が遊びや生活の中で自然に身につけていく力であり、保育士が「教える」ものではありません。大切なのは、子どもたちが自ら経験する中で表す姿をどう支えるかです。
現場で重要視される理由
なぜ10の姿が現場で重要なのでしょうか。一つは、要録や保育所児童票などの記録に直結するためです。小学校への接続に際して「どんな育ちがあったのか」を伝える指標になるのが10の姿です。
また、保護者さんへの説明に活用できるのも大きな利点です。「今日はお友だちと力を合わせてブロックを片づけました。これは協同性の育ちにつながります」と具体的に伝えると、日々の小さな行動が意味ある学びだと理解してもらえます。
さらに、職員同士で共通の言葉を持つことで、園全体の教育観をそろえることができます。「この子の姿をどう見取るか」という視点が共有できれば、園児の育ちを支えるチーム力も高まります。
10の姿を日常保育に落とし込むポイント
遊びと生活を基盤に考える
10の姿は、特別なカリキュラムではなく、毎日の遊びや生活の中にこそ育ちます。砂場で友だちとトンネルを作る、散歩で道端の花を見つける、当番活動で給食を配る…。これら一つひとつが10の姿とつながっています。
保育士ができるのは、その行為を価値ある育ちとして受け止めることです。「ただ遊んでいる」ではなく「協同性が見えている」と視点を切り替えるだけで、保育の意味づけが変わります。
姿を見取る視点を持つ
「姿を見取る」とは、子どもの小さな行動を丁寧に観察し、育ちの意味を見出すことです。例えば「友だちにハンカチを貸した」という行動は、思いやりや協同性の芽生えと見取れます。
記録には「貸してあげた → 協同性」「役割を引き受けた → 自立心」といったように、具体的な行動と姿をつなげて書くと説得力が増します。
一人ひとりの育ちに合わせる
10の姿はあくまで「全体像」です。全員が同じように表すわけではありません。一人で遊ぶことが好きな子もいれば、積極的にリーダーシップをとる子もいます。それぞれの個性を尊重しながら、その子なりの育ちを支えることが大切です。
保育士は「まだできない」と焦るのではなく、「今はこの段階にいるんだな」と受け止め、次につながる環境や声かけを工夫していきましょう。
各項目ごとの実践例
「健康な心と体」― 戸外遊びや生活習慣の中で
園児にとって毎日の戸外遊びは欠かせない学びの場です。体を動かすことで筋力や持久力が育ち、自然の中で気持ちをリフレッシュできます。例えば、鬼ごっこで走り回る中で「転んでも立ち上がる」「汗をかいても楽しむ」といった姿は、健康な心と体の基盤を表しています。
また、食事や睡眠などの生活習慣も大切な要素です。「自分で手を洗う」「野菜をひと口食べてみる」など小さな挑戦を支える声かけは、子どもが自分の体を大切にしようとする意識につながります。
「自立心」― 衣服の着脱や当番活動を通して
自分でやってみようとする気持ちを育てるのが自立心です。衣服の着脱や荷物の整理など、毎日の生活の中にたくさんのチャンスがあります。
ある園児が「ボタンを自分で留めたい」と挑戦したときに、保育士が「ゆっくりでいいよ」と見守ることで、自信を持ってやり遂げる姿が見られます。失敗も含めて挑戦を尊重することが、自立心を支える大切な関わりです。
当番活動も効果的です。「お茶を配る」「出欠をとる」などの役割を任されると、子どもは責任を感じながら取り組みます。
「協同性」― 共同制作やごっこ遊びから
協同性は、友だちと一緒に活動する中で自然に表れます。例えば、大きな模造紙に絵を描くとき、子どもたちは「ここに描いていい?」「色を貸して」とやりとりを重ねます。ごっこ遊びでは「店員役」と「お客さん役」を分担し、役割を通じて関わりを学びます。
保育士は「一緒に運ぶと早いね」「交代して遊べるね」と声をかけることで、子どもたちが協力する楽しさを実感できるよう支えます。
「道徳性・規範意識の芽生え」― 約束やルールを理解する
園生活では、さまざまなルールや約束があります。「順番を待つ」「使ったおもちゃを片づける」など、日常の中で繰り返し経験することが規範意識につながります。
例えば、絵本の読み聞かせ中に「静かに聞こうね」と伝える場面。最初は守れない子もいますが、友だちの姿を見て少しずつ理解していきます。大切なのは「守れなかった」ことを責めるのではなく、「次はどうしたらいいかな」と一緒に考える姿勢です。
「社会生活との関わり」― 地域や異年齢との交流
園の外との関わりは社会性を広げる大きな機会です。散歩中に地域の人へ挨拶をする、近隣の高齢者施設を訪問するなどの経験は、「社会とつながっている」という実感を与えます。
また、異年齢での活動も有効です。年長児が年少児を手助けする姿や、年少児が年長児に憧れる姿は、互いに育ちを支え合う貴重な関わりです。
「思考力の芽生え」― 自然観察や製作活動で
虫を観察したり、葉っぱを集めて形を比べたりする活動は、子どもの「なぜ?」を引き出します。製作活動でも「どうすれば倒れないかな」「もっと高くするには?」と考える場面があります。
保育士が「どう思う?」と問いかけることで、考えを言葉にする機会が増えます。答えを与えるのではなく、一緒に試す姿勢が思考力の芽生えを支えます。
「自然との関わり・生命尊重」― 四季の移ろいや生き物の世話
園庭で花を植えたり、虫を飼ったりする体験は、自然や生命の大切さを感じる学びです。「水をあげないとしおれてしまう」「虫の命は限られている」と気づくことで、生命尊重の気持ちが芽生えます。
散歩で落ち葉を拾い「きれいだね」と共感することも自然との関わりです。小さな発見を一緒に喜ぶことで、豊かな感性が育ちます。
「数量や図形、文字などへの関心・感覚」― 遊びを通じて数や形を楽しむ
ブロックを数える、おはじきを分ける、絵本で文字に親しむ…。こうした遊びは数量や図形、文字への関心を自然に育みます。「○個あるね」「丸と三角を組み合わせてみよう」など、日常のやりとりに取り入れると無理なく学びにつながります。
「言葉による伝え合い」― 発表や日常の対話から
「楽しかったことを話す」「友だちにお願いする」など、言葉で伝える経験は日常にあふれています。朝の会や帰りの会で話す場面、友だちと遊びながら意見を交わす場面は、言葉による伝え合いの力を育てます。
保育士は「よく伝えられたね」「お友だちの話を聞けたね」とフィードバックし、伝え合う喜びを強めていきます。
「豊かな感性と表現」― 音楽・絵画・身体表現を楽しむ
歌やダンス、絵画などを通して自由に表現することは、感性を育てる大切な体験です。「自分なりの表現が受け入れられる」という安心感が、創造的な活動を後押しします。
発表会などの行事だけでなく、日常の中で「歌いたい」「描きたい」と思う気持ちを尊重することが、感性を支える土台になります。
保育士が直面する課題と工夫
姿が見えにくいときの捉え方
10の姿は、はっきりと形になることもあれば、とても小さな兆しとして表れることもあります。例えば「協同性」を見ようとしても、派手な共同制作の場面ばかりに目が行ってしまいがちです。けれど、実際は「ブロックを貸してあげた」「泣いている友だちにティッシュを渡した」といったささやかな行動に協同性の芽生えは隠れています。
保育士に求められるのは、そうした小さな姿を見取る感性です。「まだ協力できていない」ではなく「今はこういう形で表れている」と受け止めることで、子ども一人ひとりの育ちを支えることができます。
保護者さんへの説明に悩むとき
保護者さんに10の姿を説明する際、「専門用語で難しくなってしまう」「具体的に伝えられない」という声をよく聞きます。例えば「思考力の芽生え」という言葉だけでは、日常生活のどんな場面と結びついているのか分かりにくいですよね。
そこで「ブロックで高い塔を作ろうと工夫していました。その姿に思考力の芽生えが見られます」と、行動と意味をセットで伝えることが大切です。保護者さんにとってもイメージしやすく、家庭での子育てにも参考になります。
記録や要録にどう書くか
「要録に書くときにどう表現したらいいか分からない」という悩みも多いです。長い文章を書く必要はありません。「役割を引き受けて最後までやり遂げた → 自立心」「友だちと一緒に片づけた → 協同性」と短くまとめるだけでも十分です。
ポイントは「事実+解釈」を明確にすること。行動を記録し、それを10の姿と関連づけて書くことで、読み手にとって分かりやすい記録になります。
実践を支える振り返りと共有の方法
短いエピソードを積み重ねて残す
日々の保育で一度に多くの姿を残そうとすると負担が大きくなります。おすすめは「短いエピソードの積み重ね」です。1行でも2行でもいいので「今日の小さな姿」を書き残していくことが大切です。積み重ねれば、振り返りや要録に活用できる豊かな記録になります。
同僚と共有する園内研修の工夫
職員同士で「この場面はどの姿として見取れるか」を考え合う園内研修はとても有効です。例えば同じエピソードでも、ある保育士は「協同性」と見取り、別の保育士は「言葉による伝え合い」と考えるかもしれません。こうした違いを共有することで、多角的に子どもの育ちを支える視点が育ちます。
理論と実践をつなげる学びの必要性
現場での経験に加えて、理論を学ぶことも欠かせません。教育・保育要領や専門書を通じて背景や意図を理解することで、保育士自身の納得感が深まります。理論を理解していると、保護者さんへの説明や職員間の対話にも自信を持って臨めるようになります。
実践を助ける関連書籍の紹介
実践を続ける中で「この関わりで合っているのか」「もっと良い方法はないか」と迷うこともあると思います。そんなときに役立つのが、理論と事例を学べる関連書籍です。ここでは特におすすめの4冊を紹介します。
まずは、この本に書かれている内容をどんどん真似してみてくださいね。そうすることで、日々の保育の負担がぐっと減ります。
その分できた心の余裕で、自分なりの工夫を加えながら保育を改善し、子どもたち一人ひとりの育ちを支えていきましょう。
どれも教育・保育要領に沿った内容で、日々の実践や保護者さんへの説明に役立つものばかりとなっています。
『10の姿プラス5・実践解説書』の活用
子どもたちの「10の姿」をどう保育実践に活かすかを具体的に知りたい先生におすすめな本です。教育・保育要領に示された「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を、豊富なカラー写真と実践事例でわかりやすく解説。園児の育ちを支える日々の保育に直結するヒントが満載です。新人からベテランまで現場で役立つ一冊です。
『10の姿で保育の質を高める本 』で学べる視点
保育実践の質を高めたい先生におすすめな本です。教育・保育要領に示される「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」をわかりやすく解説し、日々の保育にどう結びつけるか具体的に示しています。園児の育ちを支える視点を整理したい新人から、中堅・ベテランの先生まで活用できる一冊です。
『遊びや生活のなかで“10の姿"を育む保育 』で広がる事例
教育・保育要領に示された「10の姿」を実際の保育場面と結びつけて学べる実践書です。日常の遊びや生活の中でどのように子どもたちの育ちを支えるかを、豊富な事例と写真で具体的に解説。新人保育士から経験豊富な先生まで、保育の質を高めたい方に役立つ一冊です。
『幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿』による振り返り
園児の「思いやり」「協同性」「学びに向かう力」など、「幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿」をわかりやすく解説した一冊です。日々の保育の中でどんな場面を見取り、どう育ちを支えるのかを丁寧に示してくれるので、現場の実践にすぐ役立ちます。日々読み返したくなるので保育士の学び直しにもおすすめです。
どれも専門的な内容をやさしく解説しており、新しい視点で明日からの保育の質を高めたい方にぜひ読んでほしい本となっています。
注意点とデメリットも理解しておく
無理に姿を求めすぎない
10の姿は「到達目標」ではなく「方向性」です。けれど、現場では「この子はまだ○○ができていない」と焦ってしまうことがあります。すると子どもに過度な期待をかけたり、無理に活動へ参加させたりすることにつながります。大切なのは「まだ表れていない」ではなく「これから育っていく」という視点です。子どものペースを尊重し、時間をかけて育ちを支えることが大事になります。
子ども同士を比較しない
「もう友だちと協力できている子がいるのに、うちのクラスの○○ちゃんは…」と比較してしまうこともあります。しかし成長のスピードは一人ひとり異なります。協同性や自立心などは、環境や個性によって現れる時期が違うのです。比較よりも、園児一人ひとりの小さな成長を見取って「できるようになったね」と伝える姿勢が、子どもの自己肯定感を高めます。
成果を急ぎすぎない
「1年間で10の姿をすべて見せなければ」と思うと、保育士にも子どもにもプレッシャーがかかります。大切なのは短期間で結果を出すことではなく、日常の積み重ねの中で自然に表れる姿を支えることです。「昨日よりも少し挑戦できた」という変化を認めることで、子どもの安心につながります。
保育士の価値観を押し付けない
大人が理想とする「思いやり」や「協力」の形が、必ずしも子どもの表現と一致するわけではありません。例えば「おもちゃを貸してあげる」だけが協力ではなく、「貸したくない」と意思を伝えることも自立心や自己表現の一部です。保育士は子どもたちの多様な表し方を尊重し、柔軟に受け止める必要があります。
よくある質問(FAQ)
10の姿は全員に必ず表れるの?
すべての子が同じ時期に同じように表すわけではありません。ただし一人ひとりに必ず育っていく要素です。保育士が焦らず支えれば、子どもなりの形で姿が見えてきます。
年齢ごとの違いはどう考える?
年少児では芽生えの段階、年長児ではより具体的に表れる段階といった違いがあります。同じ協同性でも、年少児は「一緒に遊びたい」、年長児は「役割分担をして協力する」といった違いが見られます。
保護者さんにはどう伝えればいい?
専門用語をそのまま使うよりも、具体的な行動とセットで伝えると理解してもらいやすいです。「靴をそろえて並べていました。これは自立心の芽生えです」といった伝え方なら、保護者さんも家庭での姿と結びつけやすくなります。
まとめ ― 明日からできる実践のヒント
教育・保育要領に示される「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」は、子どもたちの未来につながる大切な道しるべです。健康な心と体、思いやり、協同性、表現する力…。これらは特別なカリキュラムではなく、日々の遊びや生活の中に自然に育まれます。
保育士にできるのは、子どもの小さな姿を見取って、それを言葉にして返すことです。「友だちを助けてくれてありがとう」「一人でやってみようとしたね」と伝えるだけで、子どもは自分の行動に意味を感じます。保護者さんに具体的なエピソードを伝えることは、園と家庭が一体となって子どもの育ちを支えるきっかけにもなります。
また、同僚とエピソードを共有することで、園全体の教育観をそろえることができます。そして迷ったときは関連書籍を手に取り、理論や他の実践例を学ぶことで、自信を持って保育に向き合えるようになります。
協同性や思考力の芽生えなどは一朝一夕に育つものではありません。けれど「小さな姿を丁寧に見取って言葉にする」ことなら、今日から誰でも始められます。その積み重ねが、園児一人ひとりの育ちを支える大きな力になるといいですね。