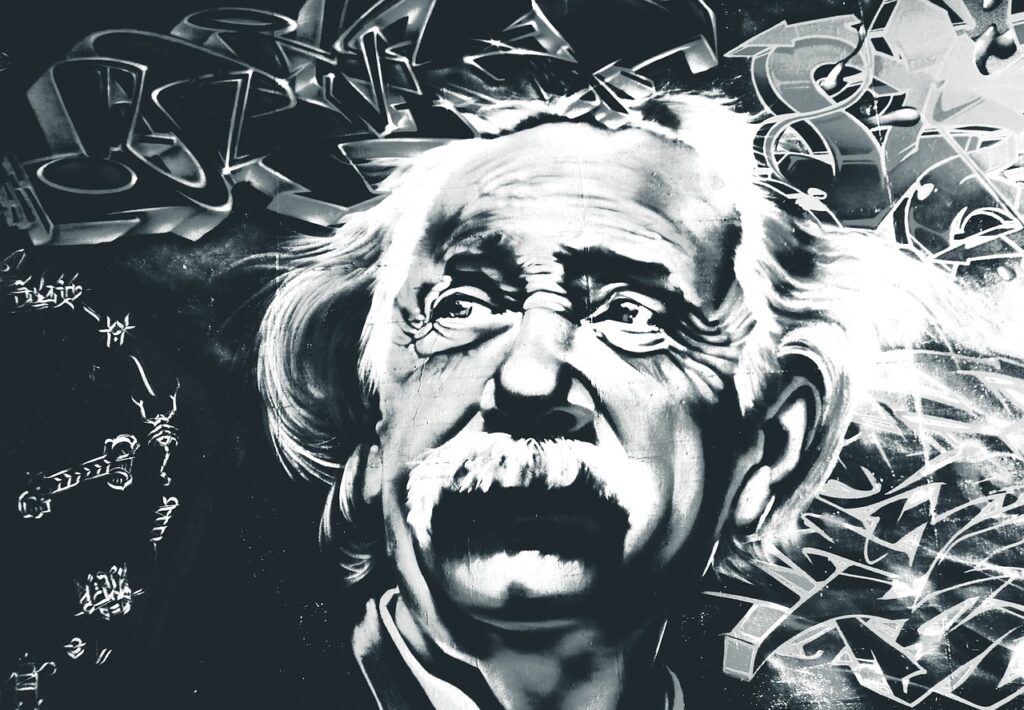
保育園やこども園での保育実践では、園児に「正しい答え」を教えることに力を入れてしまいがちです。もちろん基礎的な生活習慣や知識は大切ですが、それだけでは子どもたちの可能性を十分に広げることはできません。
末永幸歩さんの著書『「自分だけの答え」が見つかる 13歳からのアート思考』は、「正解のない問い」と向き合い、自分なりの考えを持つことの大切さを教えてくれる一冊です。この本で語られる「アート思考」とは、既存の正解に頼るのではなく、自分で問いを立て、考え続ける力を育てるものです。
この記事では、この本の内容を参考にしながら、保育士や職員が園児の「問い」を育て、育ちを支えるための具体的な保育実践の方法を紹介していきます。
👉 『「自分だけの答え」が見つかる 13歳からのアート思考』をチェックする
なぜ「問い」を大切にすることが必要なのか
知識や正解だけでは育めない力
これまで教育は「どれだけ正しい答えを出せるか」に重点を置いてきました。しかし社会で本当に求められるのは、自分の頭で考え、状況に応じて答えをつくり出す力です。『13歳からのアート思考』は、この「正解探しにとらわれない力」を子どもたちに育む重要性を説いています。
子どもたちの創造性や自分らしさを伸ばすために
「問い」を持つことは、子どもたちが自分なりの考えを形にする第一歩です。「どうして空は青いの?」「なんで鳥は飛べるの?」といった素朴な疑問は、子どもたちが世界を主体的に見ている証拠です。保育士がその問いを受け止めることで、創造性を伸ばす土台になります。
保護者さんからも期待される「考える力」
「小学校に行っても困らないように、自分で考える子になってほしい」と願う保護者さんは多いです。園で「問い」を大切にする保育を行うことは、家庭の期待にも応える取り組みとなります。
保育現場で見られる課題
正しい答えを求めすぎてしまう園児の姿
パズルやワークをしていると「これでいい?」とすぐに確認してくる園児がいます。答え合わせに依存するあまり、自分の考えを持つことに自信が持てないのです。
自分の考えを表現するのが苦手な子どもたち
「どっちが好き?」と聞かれても「どっちでもいい」と答えてしまう子もいます。正解のある質問に慣れすぎていると、自分の気持ちや考えを言葉にするのが難しくなります。
職員や同僚も「間違いを恐れる」雰囲気になりやすい
園全体で「正しいことが一番」という空気が強すぎると、子どもたちも間違いを恐れて挑戦できなくなります。職員や同僚がまずは「正解探しにとらわれない姿勢」を持つことが大切です。
『13歳からのアート思考』から学ぶ視点
正解探しよりも「問い」を楽しむ
「どうしたらもっと面白くなるかな?」といった問いを投げかけることで、子どもたちは自由に発想を広げます。本の中でも「問いを楽しむこと」がアート思考の基本であると紹介されています。
他者と違う考え方を尊重する
園児の中には、友だちと違う答えを出すことに不安を感じる子もいます。しかし「それもいい考えだね」と受け止めることで、自分の発想を肯定的に捉えられるようになります。
園児の小さな気づきを大切にする
「ここは赤にしたい」「丸じゃなくて三角にしたい」といった小さな選択も、子どもが問いを持って考えた結果です。その姿を見取り、育ちを支えることが大切です。
👉 『「自分だけの答え」が見つかる 13歳からのアート思考』を詳しく読む
保育実践に取り入れる工夫
遊びや活動の中で「問い」を投げかける関わり方
ブロック遊びのときに「どうしたらもっと高く積めるかな?」と問いかける。絵本の時間に「この後どうなると思う?」と投げかける。こうした小さな工夫が、子どもたちに考える楽しさを伝えます。
園児の姿を見取る記録と振り返りを活かす
子どもたちがどんな問いを発しているかを記録し、職員同士で共有すると、園全体で「問いを育てる保育」が進みます。同僚と振り返ることで、一人ひとりの育ちを支える関わり方が見えてきます。
保護者さんと共有して家庭でも「問い」を支える
園での問いを保護者さんに伝えることで、家庭でも同じ姿勢で支えられます。例えば「園では『どうやって音が出るのかな?』と楽器に興味を持っていました」と伝えれば、保護者さんも家庭で一緒に探究できます。
具体的な事例紹介
絵本の読み聞かせで「登場人物の気持ちはどうかな?」と問いかけたケース
ある日『三びきのやぎのがらがらどん』を読んだときに、「橋の下のトロルはどんな気持ちだったと思う?」と問いかけました。子どもたちは「怒ってる」「おなかがすいてる」とさまざまな答えを出し、物語を多角的に楽しむ姿が見られました。
工作活動で「どんな形にしたい?」と選択肢を広げた場面
画用紙を切るときに「丸にする?四角にする?それとも自由な形でもいいよ」と伝えたところ、星やハートなど自由な発想が生まれました。保育士が問いを投げることで、創造性を発揮する姿を見取ることができました。
保護者さんと協力して「家庭での問いかけ習慣」を広げた取り組み
園で「どうして空は青いの?」と話していた園児について保護者さんに伝えたところ、家庭でも一緒に調べる活動が始まりました。園と家庭が連携することで、子どもたちの学びは広がりました。
まとめ
『13歳からのアート思考』は、保育実践において「正解探しより問いを大切にする」視点を与えてくれる。
園児が持つ小さな疑問を受け止め、その姿を見取ることで、創造性や考える力を伸ばせる。
職員や同僚が問いを尊重する姿勢を持ち、保護者さんと連携して家庭でも支えることが重要。
明日からの保育実践で、園児の「どうして?」「なんで?」という声に耳を傾け、それを一緒に考える時間を大切にしてみましょう。その積み重ねが、子どもたちの可能性を大きく広げる保育につながるといいですね。
👉 『「自分だけの答え」が見つかる 13歳からのアート思考』を実際に読んでみる
