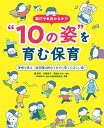「子どもたちに思いやりを育てたい。でも、どうやって日々の保育に落とし込めばいいのか分からない。」そんな風に悩んでいる保育士さんは少なくありません。
教育・保育要領では「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」として10の姿が示されています。その中の一つが「思いやりのある子」です。そして、この姿は人間関係領域と深くつながっています。
けれど実際の現場では、友だち同士のけんかや言い合い、時には手が出てしまうこともあります。そうした姿をどう受け止め、どう「思いやりの育ち」に結びつけていくのか、悩む瞬間も多いのではないでしょうか。
この記事では、「思いやりのある子」を育てる保育実践をテーマに、10の姿と人間関係領域を関連づけながら分かりやすく解説します。園児の日常の遊びや生活の中で見取れる具体例を紹介し、さらに関連書籍も取り上げて理解を深められるようにまとめています。最後まで読むことで、子どもたちの育ちを支えるために明日からできる小さな一歩を見つけられるといいですね。
「思いやりのある子」とは何か
教育・保育要領における位置づけ
教育・保育要領の「10の姿」の一つに「思いやりのある子」が挙げられています。これは単に「優しくする」ことではありません。相手の気持ちに気づき、自分なりに行動に移す姿を指しています。例えば「泣いている友だちにハンカチを渡す」「転んだ子を見て駆け寄る」といった行為は、小さな思いやりの芽生えです。
人間関係領域との関係性
人間関係領域には「人と関わる力」「友だちと協力する力」が含まれています。思いやりはその中核ともいえる要素です。子どもたちは日々の遊びや生活の中で他者との関係に出会い、衝突し、また仲直りを繰り返しながら「相手を思う心」を育んでいきます。思いやりは人間関係領域の実践を通して自然に表れる育ちなのです。
思いやりは年齢によってどう表れるか
0〜2歳児では、まだ「自分中心」で世界を見ています。けれど、泣いている友だちを見て一緒に泣く、保育士の表情をまねして「なでなで」するなど、共感の芽生えはすでに表れています。
3〜4歳児になると「貸して」「どうぞ」と言える場面が増え、少しずつ相手を意識した行動が見られます。
5歳児では、友だちの気持ちを理解して仲裁に入る、困っている友だちを助けるなど、より主体的な思いやりが見取れるようになります。年齢に応じた成長の段階を知ることで、保育士は子どもたちの育ちを支える関わりがしやすくなります。
保育士が直面する課題
子ども同士のけんかやトラブルが多い
「思いやりのある子に育ってほしい」と願っていても、実際の現場ではけんかやトラブルが絶えません。おもちゃの取り合いや順番をめぐる衝突は日常茶飯事です。保育士としては「どうやって思いやりの芽生えにつなげればいいのか」と迷うことがあります。
思いやりを「どう育てたか」を記録に残すのが難しい
週案や日誌に「思いやりが育っています」と書くのは簡単ではありません。何を根拠にそう判断するのかを具体的に記録する必要があるからです。保育士が「どんな出来事からどのような姿を見取れたか」を整理して残すことは大切ですが、時間が限られている現場では負担に感じることもあります。
保護者さんにわかりやすく伝える工夫が必要
保護者さんから「うちの子は優しい子ですか?」と聞かれたことはありませんか。そんな時に「思いやりの姿が見られます」と答えるだけでは伝わりにくいです。具体的なエピソードを交えて「泣いている友だちにティッシュを持っていっていました。その行動が思いやりの芽生えです」と伝えることで、納得感を持ってもらえるようになります。
日常保育でできる「思いやり」を育てる実践例
遊びの場面で協力や譲り合いを見取る
遊びは、子どもたちが自然に思いやりを学ぶ大切な時間です。例えばブロック遊びの場面では、「ここを持ってて」「一緒に作ろう」と声を掛け合う姿が見られます。これは単なる遊びのやりとりではなく、協力する力や相手の気持ちを尊重する姿を見取れる瞬間です。
一方で、おもちゃの取り合いも日常的に起こります。大人の視点では「けんか」と見えますが、実は「相手とどう関わればいいか」を学んでいる大切な経験です。保育士が「どうしたら一緒に遊べるかな?」と問いかけることで、子どもたちは譲り合いや解決策を自分たちで考えようとします。
生活習慣の中で「ありがとう」「ごめんね」を体験する
思いやりは特別な場面でだけ育つものではありません。日常の生活習慣の中にもたくさんの芽があります。給食の配膳で「どうぞ」と渡す、友だちから手伝ってもらった時に「ありがとう」と言う、ぶつかってしまったときに「ごめんね」と言う。こうした小さなやりとりが、心のやわらかさを育てていきます。
保育士が「ありがとうって言ってくれたね。うれしいね」と言葉を添えることで、子どもは「自分の行動が相手を喜ばせる」と実感します。こうした積み重ねが、思いやりの基盤になります。
保育士の言葉がけで子どもたちの気づきを促す
大人のかかわりは、思いやりを育てる上で大きな役割を持っています。例えば、泣いている子に気づいた園児に対して「声をかけてくれてありがとう。○○ちゃん、うれしいと思うよ」と伝えると、その子は自分の行動に意味を感じ、自信を深めます。
逆に、子どもの行動を見逃してしまうと、せっかくの思いやりの芽が気づかれず終わってしまうこともあります。保育士がその瞬間を見取り、言葉にして返すことで、子どもたちは「人に優しくすることの価値」を体験的に学びます。
小さな成功体験を積み重ねて自信につなげる
「思いやりのある子」を育てるには、子どもたちが「自分は人の役に立てる」という実感を持てることが大切です。例えば「泣いていた友だちにおもちゃを貸したら笑顔になった」という経験は、その子にとって大きな成功体験です。保育士が「友だちの気持ちに気づいてくれたんだね」と言葉で肯定すると、さらに自信が深まり、次の思いやりにつながります。
こうした積み重ねが、園児の中に「人に優しくすることはうれしい」という価値観を自然に育んでいきます。
実践を助ける関連書籍の紹介
『10の姿プラス5・実践解説書』の活用
子どもたちの「10の姿」をどう保育実践に活かすかを具体的に知りたい先生におすすめな本です。教育・保育要領に示された「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を、豊富なカラー写真と実践事例でわかりやすく解説。園児の育ちを支える日々の保育に直結するヒントが満載です。新人からベテランまで現場で役立つ一冊です。
『10の姿で保育の質を高める本 』で学べる視点
保育実践の質を高めたい先生におすすめな本です。教育・保育要領に示される「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」をわかりやすく解説し、日々の保育にどう結びつけるか具体的に示しています。園児の育ちを支える視点を整理したい新人から、中堅・ベテランの先生まで活用できる一冊です。
『遊びや生活のなかで“10の姿"を育む保育 』で広がる事例
教育・保育要領に示された「10の姿」を実際の保育場面と結びつけて学べる実践書です。日常の遊びや生活の中でどのように子どもたちの育ちを支えるかを、豊富な事例と写真で具体的に解説。新人保育士から経験豊富な先生まで、保育の質を高めたい方に役立つ一冊です。
『幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿』による振り返り
園児の「思いやり」「協同性」「学びに向かう力」など、「幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿」をわかりやすく解説した一冊です。日々の保育の中でどんな場面を見取り、どう育ちを支えるのかを丁寧に示してくれるので、現場の実践にすぐ役立ちます。日々読み返したくなるので保育士の学び直しにもおすすめです。
どれも専門的な内容をやさしく解説しており、新しい視点で明日からの保育の質を高めたい方にぜひ読んでほしい本となっています。
よくある質問(FAQ)
「思いやり」は必ず育つもの?
思いやりは自然に芽生える部分もありますが、環境や関わりによって大きく変わります。例えば、周囲から「ありがとう」と言われる経験が多い子は、人を助けることに喜びを感じやすくなります。逆に、自分の行動が気づかれなかったり否定されると、自信をなくしてしまうこともあります。大切なのは、保育士がその芽を見取り、言葉でしっかり伝えることです。
けんかの場面はどう関わればいい?
けんかは悪いことではなく、思いやりを学ぶ大切なきっかけです。「だめ!」と止めるだけでなく、「どうしたかったの?」「どうしたら一緒に遊べるかな?」と問いかけることで、相手の気持ちに気づく場となります。けんかの後に仲直りする経験も、思いやりを育てる大切なプロセスです。
記録や週案にはどう反映すればいい?
「友だちが転んだときに駆け寄っていた→思いやりの芽生え」と短く書くなど、出来事と結びつけて残すと分かりやすくなります。抽象的に「優しい行動が見られた」と書くよりも、具体的な場面を記録することで、同僚や保護者さんに伝わりやすくなります。
注意点とデメリットも理解する
形だけの「優しくしよう」にならないようにする
「思いやりを持ちなさい」と言葉で指導するだけでは、子どもの心には響きません。大人が押しつけるのではなく、子ども自身が「相手が喜んでくれてうれしい」と実感する体験が大切です。形だけの声かけにならないよう、日々の小さなエピソードを大切にしましょう。
子ども同士を比較しない
「○○ちゃんは優しいのに、あなたはできないの?」といった比較は、子どもの自己肯定感を傷つけてしまいます。思いやりは一人ひとりのペースで育つものです。他の子と比べるのではなく、その子自身の育ちを見取る視点が求められます。
保育士の価値観を押し付けない
「こうするのが優しい子」という大人の基準を押しつけすぎると、子どもが自分なりの表現をしにくくなります。例えば「貸してあげなさい」と強制するのではなく、「どうしたい?」と問いかけることで、子どもが自分で考え、選択できる余地を残すことが大切です。
まとめ ― 今日からできる一歩
「思いやりのある子」を育てることは、教育・保育要領に示された10の姿の一つであり、人間関係領域と深く結びついています。思いやりは特別な行事で育つものではなく、日常の遊びや生活習慣、そして小さなエピソードの積み重ねの中で育まれます。
明日からできる一歩として、まずは園児の小さな思いやりの行動を一つ見取ってみてください。そして、その姿を言葉にして返すことを意識してみましょう。「友だちに声をかけてくれたね。きっとうれしいと思うよ」と伝えるだけで、子どもは自分の行動に自信を持ちます。
同僚とその気づきを共有することで、園全体で子どもの育ちを支える文化が広がっていきます。また、保護者さんには具体的なエピソードを添えて伝えることで、家庭との信頼関係も強まります。
今回紹介した関連書籍を活用すれば、日常の実践を「10の姿」と結びつけて振り返ることができ、保育の質をさらに高められます。すべてを完璧にしようとせず、一歩ずつ、子どもたちの育ちを支える実践を積み重ねていけるといいですね。