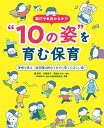「子どもたちにもっと協力する力をつけてあげたい。でも現場ではけんかやトラブルが多くて、どう支えていいのか分からない…」そんな思いを抱える保育士さんも多いのではないでしょうか。
教育・保育要領に示される「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の一つに「協同性」があります。これは、友だちと関わり合い、力を合わせながら活動する中で育つ大切な姿です。単に「仲良くする」だけではなく、「一緒に取り組む中で考えたり感じたりしながら学んでいく」ことが求められています。
しかし実際の保育現場では、子どもたちがうまく協力できずに衝突する場面や、一人で過ごすことを好む園児も多くいます。そうしたとき、保育士はどんな視点で支えればよいのでしょうか。この記事では、協同性とは何かを教育・保育要領の観点から整理し、共同制作やごっこ遊び、生活の中での実践を具体的に紹介します。さらに、振り返りや同僚との共有、理論を補うための書籍の活用についても触れます。読み終えたときに「明日からすぐできる一歩」を見つけていただけるといいですね。
協同性とは?教育・保育要領の観点から
「10の姿」における協同性の位置づけ
教育・保育要領では「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」として10項目が示されています。その中で「協同性」とは「友だちや周囲と関わり合いながら、共に活動する姿」と説明されています。これは単なる協力作業ではなく、相手の存在を認識し、気持ちを受け止め、共に生きる力を身につけていくことを意味します。
例えば「一緒に砂場で山を作る」「友だちと順番にすべり台を滑る」といった日常の場面に協同性は隠れています。小さな「やりとり」の積み重ねが、子どもたちの人間関係力を育てていくのです。
人間関係領域との関連性
協同性は「人間関係領域」と深く結びついています。この領域のねらいは「人と関わる力を育てる」こと。具体的には「仲間と一緒に遊ぶ」「思いを伝え合う」「互いに認め合う」といった経験を通して、子どもたちは協同性を育んでいきます。
例えば、ある園でのごっこ遊び。子どもたちが「今日はレストランごっこしよう」と始めると、自然と「お客さん役」「店員役」に分かれます。ここで生まれる「順番を待つ」「役割を果たす」といったやりとりは、まさに協同性の実践です。
協同性が育つと期待できる子どもの姿
協同性が育っていくと、子どもたちには次のような姿が見られます。
友だちと相談しながら活動を進める
困っている友だちを助ける
自分の考えを伝えながら相手の意見も聞く
一緒に取り組んだ達成感を味わう
こうした姿を見取ることは、保育士にとっても大切な視点です。なぜなら、協同性は社会に出てからも必要とされる「共に生きる力」の基盤だからです。
保育士が直面する課題と悩み
けんかや衝突が多いときどう考えるか
現場でよくあるのは「けんかが多くて困る」という悩みです。しかし実は、けんかや衝突は協同性を学ぶチャンスです。自分の気持ちを相手に伝えたり、折り合いをつけたりする過程そのものが学びです。
保育士は「けんか=悪いこと」と決めつけず、「どうしたかったの?」「相手はどう思ったかな?」と問いかけることで、子どもが気持ちを整理し、相手との関係を築くきっかけにできます。
一人遊びが好きな園児への対応
協同性を大切にする一方で、一人で遊ぶことを好む子どももいます。「協力させなければ」と無理にグループに入れると、安心感を失い逆効果になることもあります。
大切なのは「その子なりの関わりの芽」を見取ることです。例えば、一人で積み木をしていても、隣の友だちの真似をする瞬間があります。そうした小さな関わりを大事にしながら、少しずつ広げていくことが保育士の役割です。
記録や保護者さんへの説明に困るとき
「協同性は目に見えにくいので、記録や保護者さんへの説明が難しい」と悩む声も多いです。その場合は「具体的なエピソード」を短く残すことが有効です。
例:「ブロックを一緒に運び、友だちに『こっちだよ』と声をかけていた → 協同性の芽生え」
このように「行動+育ちの意味」を記録することで、後から振り返っても分かりやすく、保護者さんにも伝わりやすくなります。
日常保育で協同性を育む具体的実践
共同制作活動 ― 大きなものを一緒に作る体験
協同性を育む場面として代表的なのが、みんなで一つの作品を仕上げる共同制作です。大きな模造紙に絵を描く、段ボールで町やお城を作る、壁面装飾をクラス全員で仕上げるといった活動は、一人では成し得ない体験です。
例えば段ボールで街を作る活動。ある子は「おうちを作る」、別の子は「道を描きたい」と自分の役割を自然に見つけていきます。保育士は「誰がここを担当する?」「一緒に持てば運べそうだね」と声をかけることで、子ども同士のやりとりを引き出せます。
こうした体験は「友だちと相談する」「自分の意見を出す」「相手の工夫を取り入れる」といった協同性の土台を築きます。
ごっこ遊び ― 役割分担を通じて学ぶ関わり
ごっこ遊びも協同性を育てる絶好の場です。レストランごっこを例にすると、子どもたちは自然と「店員役」「お客さん役」に分かれます。この中で「順番を守る」「役割を果たす」「交代する」といった経験を積むことができます。
トラブルが起きたときに大人がすぐに解決してしまうのではなく、「どうすればみんなで遊べるかな?」と問いかけることで、子どもたちは自分たちで折り合いをつける練習ができます。ごっこ遊びは想像力を広げるだけでなく、人との関わり方を実感できる貴重な時間です。
生活の場面 ― 給食や片づけの中で協力を学ぶ
協同性は特別な活動だけでなく、日常生活の中にこそ育ちます。給食で「友だちのトレーを一緒に運ぶ」「配膳を手伝う」、片づけで「重たい箱を協力して片づける」といった行動は小さな協力の積み重ねです。
保育士が「一緒に運んでくれてありがとう」「友だちが助かってうれしそうだったね」と声をかけることで、子どもは「協力すると喜ばれる」という実感を得ます。こうした小さな積み重ねが、協同性を大きく育てていきます。
保育士の言葉かけ ― 小さな協力を見逃さない
協同性を育てるうえで大切なのは、保育士が子どもの小さな協力を「見取る」ことです。例えば、泣いている友だちにハンカチを渡したり、落ちた鉛筆を拾ってあげたりする姿。こうした一見些細な行動も協同性の芽です。
「友だちの気持ちに気づいたんだね」「助けてもらって嬉しかったね」と具体的に伝えることで、子どもは「人と関わる喜び」を感じ、さらに協力する意欲につながります。
実践を深めるために必要な視点
子どもの姿を見取るための振り返り
協同性は「できた・できない」で評価するものではなく、日常の中で表れる子どもの姿をどう見取るかが重要です。たとえば「ブロックを一緒に運ぼうと声をかけた」「役割を譲った」などの具体的な行動を記録しておくと、振り返りの質が深まります。
短いエピソードを積み重ねることで、保育士自身が子どもの育ちを再確認でき、同僚や保護者さんに伝える際にも説得力が増します。
同僚と共有することで気づきが広がる
一人の視点では見えにくい子どもの育ちも、同僚と共有することで新しい発見があります。「あの子は家では一人遊びが多いけど、園では友だちに声をかけていた」など、園と家庭の姿をつなげて理解できることもあります。
園内研修で協同性をテーマに事例を持ち寄って話し合うと、子どもたちの育ちを支える視点が職員全体で共有できます。こうした取り組みは、園全体で「協同性を大切にする文化」を築く一歩になります。
理論や事例を学び、実践に活かす必要性
実践を重ねる中で「これでいいのかな?」と不安を抱く保育士も多いでしょう。そのときに役立つのが書籍や専門資料です。理論を理解し、他園の実践事例に触れることで、今の自分たちの取り組みに自信を持つことができます。
また、保護者さんに説明するときも「教育・保育要領に示されている協同性を、こういう場面で育んでいます」と伝えられると信頼感が高まります。つまり、理論を知ることは実践を確かにし、保護者さんや同僚とのコミュニケーションにもつながるのです。
実践を支える関連書籍の紹介
協同性を育てる実践を深めるには、現場での経験だけでなく、理論的な裏づけや他園の事例を学ぶことが大きな支えになります。ここでは、おすすめの関連書籍を4冊紹介します。どれも教育・保育要領に沿った内容で、日々の実践や保護者さんへの説明に役立つものばかりです。
『10の姿プラス5・実践解説書』の活用
子どもたちの「10の姿」をどう保育実践に活かすかを具体的に知りたい先生におすすめな本です。教育・保育要領に示された「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を、豊富なカラー写真と実践事例でわかりやすく解説。園児の育ちを支える日々の保育に直結するヒントが満載です。新人からベテランまで現場で役立つ一冊です。
『10の姿で保育の質を高める本 』で学べる視点
保育実践の質を高めたい先生におすすめな本です。教育・保育要領に示される「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」をわかりやすく解説し、日々の保育にどう結びつけるか具体的に示しています。園児の育ちを支える視点を整理したい新人から、中堅・ベテランの先生まで活用できる一冊です。
『遊びや生活のなかで“10の姿"を育む保育 』で広がる事例
教育・保育要領に示された「10の姿」を実際の保育場面と結びつけて学べる実践書です。日常の遊びや生活の中でどのように子どもたちの育ちを支えるかを、豊富な事例と写真で具体的に解説。新人保育士から経験豊富な先生まで、保育の質を高めたい方に役立つ一冊です。
『幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿』による振り返り
園児の「思いやり」「協同性」「学びに向かう力」など、「幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿」をわかりやすく解説した一冊です。日々の保育の中でどんな場面を見取り、どう育ちを支えるのかを丁寧に示してくれるので、現場の実践にすぐ役立ちます。日々読み返したくなるので保育士の学び直しにもおすすめです。
よくある質問(FAQ)
協同性はすべての子どもに自然に育つの?
はい、協同性は誰にでも育つ可能性がありますが、その表れ方やスピードには個人差があります。一人遊びを好む子にも、ふとした瞬間に「友だちの遊びを真似する」「道具を貸してあげる」といった関わりが芽生えます。保育士がその小さな姿を見取って丁寧に伝えることが、育ちを支える第一歩です。
トラブルが多い子ども同士にはどう対応すればいい?
けんかや衝突は協同性を育む大切な学びの機会です。大人がすぐに仲裁してしまうのではなく「どうしたかったの?」「相手はどう思ったかな?」と問いかけることで、子どもたちは自分で解決する力を養います。もちろん、安全を確保したうえで、やりとりそのものを経験として大切にする視点が必要です。
保護者さんにはどう伝えれば理解してもらえる?
協同性は抽象的に「育っています」と伝えても分かりにくいものです。そのため「給食のときに友だちのトレーを一緒に運んでくれました。その姿に協同性の芽生えを感じました」と、具体的なエピソードを交えて伝えると理解が深まります。家庭でも「ありがとう」と伝える習慣につながり、園と家庭が一体となって育ちを支えることができます。
記録に残すときのポイントは?
「行動+意味」を短く書くことがポイントです。
例:「一緒に積み木を運び、友だちと笑い合った → 協同性の芽生え」
こうした記録は振り返りや園内研修でも役立ち、保育士同士の学び合いにもつながります。
実践と理論をつなぐために
協同性を育てる実践は、日々の小さな積み重ねによって成り立っています。しかし「この支援でいいのかな」「もっとできることはないか」と迷うこともあります。そのときに役立つのが、こうした書籍や専門資料です。
現場の実践を振り返りながら理論を確認することで、職員自身の学びにもなり、保護者さんや同僚に自信を持って説明できるようになります。書籍を活用することは、保育士にとっても「協同性を支えるための協働」といえるでしょう。
注意点とデメリットも理解しておく
協力を強制しないこと
協同性を育てたいあまり、「みんなでやろう」「協力しなさい」と保育士が強制してしまうことがあります。しかし、子どもにとっては「やらされている」と感じてしまい、結果的に関わりを避ける原因になることもあります。協力は自発的な気持ちから生まれるもの。保育士は「一緒にやったら楽しそうだね」と提案したり、「助けてくれてありがとう」と気持ちを言葉にしたりすることで、子どもが自然と関わりたくなる環境を整えることが大切です。
子ども同士を比較しないこと
「○○ちゃんはもう友だちと協力できているのに」という比較は、子どもの自己肯定感を下げてしまいます。協同性の表れ方やタイミングは一人ひとり異なります。大切なのは、園児一人ひとりの小さな姿を見取って、その子なりの育ちを支えることです。比較ではなく、個々の成長を温かく見守る姿勢が求められます。
保育士の価値観を押し付けないこと
大人が思う「協力」と子どもが感じる「協力」は必ずしも一致しません。大人が期待する形を押し付けると、子どもが自分なりに考えたり工夫したりする余地を奪ってしまいます。保育士は「この関わり方も協力の一つなんだ」と受け止める柔軟さを持ち、子どもが自分の方法で関わることを尊重する必要があります。
成果を急ぎすぎないこと
協同性はすぐに育つものではなく、日々の積み重ねが必要です。短期間で「協力できる子にしよう」と焦ると、子どもにも保育士にもプレッシャーになります。長い目で見て「昨日より少し友だちと関わった」「前よりも声をかけられた」といった小さな変化を認めることが、安心につながります。
まとめ ― 明日からできる一歩
協同性は、教育・保育要領に示された「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の中でも、人間関係を育てるうえで欠かせない力です。共同制作やごっこ遊び、給食や片づけといった日常生活の中で、子どもたちは少しずつ「協力する楽しさ」を学んでいきます。
保育士ができることは、子どもの小さな協力の姿を見取って、丁寧に言葉で返すことです。たとえば「一緒に持ってくれて助かったよ」「友だちのことを考えられたね」と伝えるだけで、子どもは「協力することっていいことなんだ」と実感できます。その積み重ねが協同性の育ちを支えます。
また、同僚とエピソードを共有することも重要です。職員同士で視点を合わせ、園全体で子どもたちの育ちを支える姿勢を持つことで、協同性はさらに確かなものになっていきます。そして、保護者さんに具体的なエピソードを伝えることで、家庭と園が一体となって子どもの育ちを支えられるようになります。
実践に迷いが生じたときは、関連書籍を手に取って理論や他園の実例を学ぶことが大きな助けになります。学びを重ねることで、保育士自身も自信を持ち、日々の保育に向き合うことができます。
協同性は一朝一夕で身につくものではありません。ですが、今日から「小さな協力を見取って伝える」ことならすぐに始められます。その一歩を積み重ねながら、子どもたちの育ちを支える協同性の保育を実践していけるといいですね。