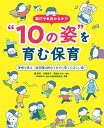「教育・保育要領にある“10の姿”は大切だとわかっているけれど、実際の保育にどう落とし込めばいいのか迷ってしまう」――そんな思いを抱えていませんか。
保育士の現場では、日々の遊びや生活の中で園児の成長を見取ることが求められます。しかし「健康な心と体」や「協同性」「思考力の芽生え」など、抽象的な言葉で示された10の姿を、実際の活動や記録につなげるのは簡単ではありません。
「どうやって保護者さんに説明すれば伝わるのか」「同僚と共有するときにどんな言葉を使えばいいのか」と悩む職員も少なくありません。
この記事では、教育・保育要領に示される10の姿を一つひとつ分かりやすく整理し、遊びや生活の中でどのように見取れるか具体例を交えて紹介します。また、保護者さんへの説明や記録づけ、園内での共有に役立つヒントもまとめました。
「明日からすぐに活かせる実践」を意識して書いていますので、どうぞ最後まで読んでいただけたらと思います。
「10の姿」とは?基本の理解
教育・保育要領における位置づけ
「10の姿」とは、幼児期の終わりまでに育ってほしい子どもの姿を教育・保育要領が示したものです。これは具体的な到達目標ではなく、子どもたちの成長を見取るときの方向性を示しています。
たとえば「思いやりのある子」という姿は、特定の行動を指すのではなく、日常生活の中で相手を気づかう表現や行動を通して少しずつ表れていくものです。保育士は「姿を見取る」視点を持ち、園児が成長している過程を丁寧に受け止めることが求められます。
10の姿が示す「方向性」とは
10の姿は「子どもが将来社会を生きる力の土台」を意識して設定されています。学力や知識に直結するものではなく、「健康な心と体」「自立心」「協同性」「思考力の芽生え」など、人としての基本的な資質を育むことを目的としています。
このため「できる/できない」で判断するものではありません。小さな表れをどう受け止めるか、どう次につなげるかが大切なのです。
「目標」ではなく「育ちを見取る視点」
多くの保育士が陥りがちなのは、「10の姿を達成させなければ」というプレッシャーです。しかし要領は「目標」として示しているのではなく、子どもを理解するための「視点」として示しています。
たとえば「言葉による伝え合い」がまだ不十分に見える園児も、表情や身振りで気持ちを伝えているかもしれません。それも立派な姿の一部です。保育士はその子なりの表現を尊重し、そこから育ちを支えることが大切になります。
日常保育で見取れる具体的な場面
遊びの中で育まれる姿
ごっこ遊びでは「協同性」や「思いやりのある子」が自然に表れます。例えば「お店屋さんごっこ」で「次はあなたが店員さんね」と交代する姿には、相手を尊重する心が見えます。ブロック遊びでは「思考力の芽生え」が表れます。「もっと高くしよう」「崩れないように工夫しよう」という試行錯誤は、探究心や思考力につながります。
製作活動では「表現する力」が大きく育ちます。折り紙や絵画で自分の思いを形にする過程には、自分らしさを大切にする姿が込められています。
生活の中で表れる姿
日常の生活の中でも10の姿は数多く見取れます。食事の前に自分で手を洗う、着替えを一人でやってみる、といった行動は「自立心」の育ちです。お当番活動で「牛乳を配る」「出席カードを集める」といった役割を果たすことも、責任感や協同性を育てる大切な体験です。
掃除や片づけの場面でも注目できます。「自分が使ったものを自分で片づける」姿からは、自立心と規範意識の芽生えが見取れます。また、友だちと協力して机を拭く姿は、協同性と社会性の表れです。
保護者さんとの関わりに表れる姿
園での姿だけでなく、保護者さんとのやりとりの中にも10の姿が見えます。たとえばお迎えのときに「今日は○○したよ」と自分から伝える姿は「言葉による伝え合い」です。また、保護者さんに甘えながらも「園で頑張った自分」を見てもらいたい気持ちは、自己肯定感の表れともいえます。
保育士はそうした場面をしっかり捉え、保護者さんにフィードバックすることで、家庭と園がつながり、子どもの育ちを支える力がより大きなものとなります。
領域とのつながりを意識した実践ヒント
5領域と10の姿の対応関係
教育・保育要領に示されている「健康・人間関係・環境・言葉・表現」という5領域は、10の姿と深くつながっています。例えば「健康な心と体」は健康領域、「思いやりのある子」は人間関係領域、「思考力の芽生え」は環境領域といったように対応させて考えることができます。
この対応を意識することで、日案や週案のねらいを立てるときに整理しやすくなります。保育士が「今日の活動はどの領域につながっているのか」を意識して書くと、10の姿をより具体的に見取れるようになります。
保育士が声かけで工夫できるポイント
活動を通して子どもの姿を引き出すには、保育士の言葉かけが大きな役割を持ちます。例えば「すごいね」「上手だね」と結果だけを褒めるのではなく、「最後まであきらめなかったね」「友だちに譲ってあげられたね」とプロセスや行動に目を向けることが大切です。
こうした声かけは「自己肯定感」や「協同性」といった10の姿を確かに育てます。日常の一言一言が子どもたちの成長に直結することを意識できるといいですね。
記録や要録につなげる具体例
「今日の活動で子どもがどう育っていたか」を文章化するのは、多くの保育士が悩む部分です。10の姿を軸にすると、観察を言葉にしやすくなります。
例)
「友だちと協力して積み木を高く積む姿から、協同性が育っていることが見取れた」
「お当番活動で役割を果たそうとする姿から、自立心の芽生えが感じられた」
このように「出来事→姿→今後の支援」という流れで記録すると、要録や保護者さんへの説明にも活用しやすくなります。
保育士が抱える課題と工夫
「姿が見えにくい」子への関わり方
保育士の悩みとしてよくあるのは「10の姿が分かりやすく表れる子と、そうでない子がいる」ということです。活発に発言したり、友だちと積極的に関わる子は観察しやすい一方で、静かに遊ぶことを好む子や言葉が少ない子は姿を見取りにくいことがあります。
そんなときは「小さな行動に注目する」ことが大切です。例えばブロックを一人で黙々と積み重ねている子も、工夫する力や集中力が育っている姿として見取ることができます。
同僚との視点合わせと園内研修
「自分はこう見取ったけれど、同僚は違う見方をしていた」ということもあります。これは悪いことではなく、子どもの姿を多角的に見られるチャンスです。園内研修やミーティングで「この姿はどう解釈できるか」を話し合うと、チームでの共通理解が深まります。
また、新人の保育士は「どう観察すればいいか分からない」と悩むこともあります。先輩保育士が自分の観察記録を共有することで、学び合いの機会を作ることができます。
保護者さんへ説明する時の伝え方
保護者さんに伝えるときは、専門用語だけでなく、具体的な行動を交えて説明することが大切です。
例)「お友だちにおもちゃを貸してあげられました。これは“思いやりのある子”としての姿の一つなんですよ」
こうした説明なら、保護者さんも家庭での姿とつなげて理解しやすくなります。園と家庭が同じ方向を向くために、分かりやすい言葉を意識したいですね。
実践を助ける関連書籍の紹介
実践を続ける中で「この関わりで合っているのか」「もっと良い方法はないか」と迷うこともあると思います。そんなときに役立つのが、理論と事例を学べる関連書籍です。ここでは特におすすめの4冊を紹介します。
まずは、この本に書かれている内容をどんどん真似してみてくださいね。そうすることで、日々の保育の負担がぐっと減ります。
その分できた心の余裕で、自分なりの工夫を加えながら保育を改善し、子どもたち一人ひとりの育ちを支えていきましょう。
どれも教育・保育要領に沿った内容で、日々の実践や保護者さんへの説明に役立つものばかりとなっています。
『10の姿プラス5・実践解説書』の活用
子どもたちの「10の姿」をどう保育実践に活かすかを具体的に知りたい先生におすすめな本です。教育・保育要領に示された「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を、豊富なカラー写真と実践事例でわかりやすく解説。園児の育ちを支える日々の保育に直結するヒントが満載です。新人からベテランまで現場で役立つ一冊です。
『10の姿で保育の質を高める本 』で学べる視点
保育実践の質を高めたい先生におすすめな本です。教育・保育要領に示される「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」をわかりやすく解説し、日々の保育にどう結びつけるか具体的に示しています。園児の育ちを支える視点を整理したい新人から、中堅・ベテランの先生まで活用できる一冊です。
『遊びや生活のなかで“10の姿"を育む保育 』で広がる事例
教育・保育要領に示された「10の姿」を実際の保育場面と結びつけて学べる実践書です。日常の遊びや生活の中でどのように子どもたちの育ちを支えるかを、豊富な事例と写真で具体的に解説。新人保育士から経験豊富な先生まで、保育の質を高めたい方に役立つ一冊です。
『幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿』による振り返り
園児の「思いやり」「協同性」「学びに向かう力」など、「幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿」をわかりやすく解説した一冊です。日々の保育の中でどんな場面を見取り、どう育ちを支えるのかを丁寧に示してくれるので、現場の実践にすぐ役立ちます。日々読み返したくなるので保育士の学び直しにもおすすめです。
こうした書籍を活用すると、自分の保育を客観的に振り返りやすくなり、保護者さんや同僚に説明するときの裏付けにもなります。
注意点とデメリットも理解しておく
無理に姿を求めすぎない
10の姿は目標ではなく方向性です。しかし、つい「まだ育っていない」と焦ってしまうことがあります。焦りは子どもたちに不要なプレッシャーを与えてしまうため、「今は芽生えの段階」「これから育っていく」という視点を忘れないことが大切です。
子ども同士を比較しない
保育士の目から見ると「この子は協力的なのに、あの子はまだ…」と比べたくなることもあります。しかし成長のスピードや表現方法は一人ひとり異なります。他の園児との比較ではなく、その子自身の小さな変化に注目して「育ちを支える」姿勢が求められます。
成果を急ぎすぎない
「今年度のうちに10の姿をすべて見せなければ」と思うと、保育士にも園児にも無理が生じます。大切なのは、短期間での成果ではなく日々の積み重ねです。「昨日より少し挑戦できた」という小さな変化を喜び、そこに意味を見出すことが自己肯定感につながります。
保育士の価値観を押し付けない
大人が思う「理想の姿」と子どもが表す姿は必ずしも一致しません。たとえば「友だちにおもちゃを貸さない」という行動も、意思を伝える自己表現の一部です。これを否定せず、「自分の気持ちを伝えられた」という成長の側面として見取る視点が必要です。
よくある質問と回答
「10の姿は全員に表れるの?」
よく聞かれる疑問のひとつです。答えは「全員に表れるが、表れ方やタイミングはそれぞれ違う」です。子どもたちは一人ひとり異なるペースで育ちます。「協同性」が早く見える子もいれば、「自立心」が強く出てくる子もいます。すぐに見えないからといって「育っていない」と判断するのではなく、小さなサインを丁寧に見取ることが大切です。
「年齢ごとの違いはどう考える?」
年少児ではまだ芽生えの段階であることが多く、年長児にかけて徐々に育っていく姿が見られます。例えば「思考力の芽生え」は、3歳では「なぜ?どうして?」と問いかける形で表れ、5歳になると「こうすればできるのでは?」と仮説を立てて試す姿につながります。保育士は年齢ごとの発達差を理解し、期待する姿を調整することが必要です。
「保護者さんへの説明はどう伝える?」
専門的な用語をそのまま伝えても、保護者さんには分かりにくいことがあります。「今日お友だちに“どうぞ”と言えたんです。これは“思いやりのある子”という育ちにつながっているんですよ」というように、具体的な行動と結びつけて説明すると安心感につながります。園での姿と家庭での姿をリンクさせることで、家庭でも子どもの育ちを支える視点が共有できます。
「10の姿をすべて記録に残すべき?」
10の姿を網羅的に毎日記録するのは現実的ではありません。大切なのは、その日の活動やエピソードの中で印象的に見えた姿を丁寧に残すことです。焦って全てを書こうとすると「形式的な記録」になり、かえって本来の目的を見失ってしまいます。
実践を継続するための工夫
小さな変化をチームで共有する
一人の保育士だけで全員の姿を見取るのは難しいものです。同僚とエピソードを共有することで、見落としていた成長に気づけることがあります。「○○ちゃんが昨日より積極的に手を挙げていましたよ」といった情報を共有することが、園全体で子どもたちの育ちを支えることにつながります。
保育者自身も学び続ける
10の姿を理解し、活かしていくには職員自身の学びが欠かせません。園内研修や自己研修で改めて教育・保育要領を読み直したり、専門書を手に取ったりすることで新しい気づきを得られます。忙しい日々の中でも「学び直す」姿勢を大切にしたいですね。
保護者さんと一緒に育ちを支える
園で見えた姿を保護者さんに伝えると、家庭でも「昨日先生から聞いたことを意識して見てみよう」と新しい気づきにつながります。園と家庭が一体となって育ちを支えることが、子どもの安心感や自己肯定感を大きく育てます。
まとめ
教育・保育要領に示される「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿(10の姿)」は、子どもの育ちを理解し支えるための大切な指針です。目標として到達させるものではなく、日常の小さな行動から「育ちの兆し」を見取るための視点です。
遊びや生活の中で表れる姿を見逃さず、言葉にして残し、保護者さんや同僚と共有すること。それが園児一人ひとりの自己肯定感を支え、未来につながる力を育てます。
そして、実践を続けていくうえで関連書籍を活用することは、自分の視点を広げ、理論と実践を結びつける大きな助けとなります。園での小さな気づきを記録に残し、言葉にして伝えていくことを積み重ねていきたいですね。
「10の姿をどう保育に活かすか」迷ったときは、今日紹介した実践例や書籍を参考に、まずは身近な場面から取り組んでみてほしいなと思います。