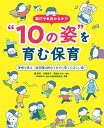「自己肯定感を育てたい」と思っても、実際に日々の保育の中でどのような声かけをすればよいのか悩む保育士さんは多いのではないでしょうか。園児一人ひとりが「自分は大切にされている」「自分にはできる力がある」と感じられることは、その後の学びや生活に大きな影響を与えます。
しかし現場では、「つい叱る言葉が先に出てしまう」「同じ言葉でも子どもによって反応が違う」といった悩みが尽きません。さらに、教育・保育要領に示される「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿(10の姿)」をどう日常に落とし込めばいいのか、迷う場面もあるでしょう。
この記事では、10の姿の視点を軸に、子どもたちの自己肯定感を育てる声かけの工夫を具体的に解説します。小さな日常の言葉がけを見直すことで、園児の育ちを支える力を高め、保護者さんへの説明や同僚との共有にも役立つ内容をお届けします。
自己肯定感とは何か?
自己肯定感とは「自分を大切な存在として受け止める気持ち」です。子どもたちにとっては「自分はできる」「認めてもらえている」という感覚が、挑戦への意欲や他者との関わりを広げる基盤になります。
例えば、絵を描いた子に「上手だね」と結果だけを伝えるより、「色を工夫して描いたんだね」とプロセスに注目した声かけをすると、「自分の工夫を見てもらえた」と感じられます。この積み重ねが自己肯定感を大きく育むのです。
自己肯定感と10の姿のつながり
教育・保育要領に示される10の姿には「自立心」「自己表現」「協同性」など、自己肯定感に深く関わる要素が含まれています。
自立心:自分でできることを増やし、自信を持つ
自己表現:考えや気持ちを伝え、「自分の存在が認められる」経験を積む
協同性:友だちと協力する中で、「自分が役に立っている」と感じる
このように、10の姿は自己肯定感の具体的な育ちを見取る視点ともいえます。
日常の声かけが育ちを支える理由
自己肯定感を育てる活動は、特別な行事やプログラムではありません。むしろ日々の生活や遊びの中での声かけこそが大切です。
たとえば、片付けを手伝った園児に「ありがとう」と言うと、その子は「自分の行動が役に立った」と感じます。遊びの中で友だちを誘ったときに「いい考えだね」と受け止めることで、「自分の思いを伝えていいんだ」と安心できます。
声かけは目に見えにくいですが、子どもたちの心の中に積み重なり、「育ちを支える」大きな力となるのです。
現場でよくある悩み
自己肯定感を育てる声かけの重要性は理解していても、実際にはうまくいかないこともあります。
褒め方が難しい
「がんばったね」ばかりになり、言葉が単調になってしまう。
否定的な言葉が先に出てしまう
危険を防ごうとして「ダメ!」「やめなさい」が増えてしまう。
子どもによって反応が違う
同じ言葉でも素直に受け止める子もいれば、照れて反発する子もいる。
保護者さんに伝えにくい
「園で育てている自己肯定感」をどう説明すれば理解してもらえるのか迷う。
こうした悩みは多くの保育士さんが感じているものであり、声かけを工夫する大切さを改めて実感させます。
解決法 ― 自己肯定感を育てる声かけの工夫
現場で感じる悩みを少しでも和らげるために、日常保育で取り入れやすい声かけの工夫を紹介します。特別な準備をする必要はなく、園児の姿を見取って、そこに適した言葉を添えるだけで十分です。
結果よりもプロセスを認める
「できた・できない」に注目するのではなく、挑戦している姿や工夫している過程を言葉にすることが大切です。
例:「最後までやりきろうとしていたね」「自分で考えてやってみたんだね」
こうした言葉は、「自分の努力を見てもらえている」という安心感につながります。
職員や同僚と「どんな場面でプロセスを認める声かけができたか」を振り返ると、より実践に定着しやすくなります。
子ども自身の言葉を引き出す
「やってみてどうだった?」「どんな気持ちになった?」と問いかけると、園児は自分の気持ちを言葉にする練習ができます。言語化することで、自分の考えを尊重してもらえる感覚が芽生え、自己肯定感を育てる土台になります。
例えばブロック遊びで塔を崩してしまった子に「どうしたらうまくいくと思う?」と聞いてみると、次の挑戦につながります。
小さな成功を積み重ねる
日常の生活の中には、自己肯定感を高めるチャンスがたくさんあります。
自分で靴を履けた
苦手な野菜を一口食べられた
友だちに「貸して」と言えた
これらを見逃さずに「できたね」と伝えることで、「自分にもできるんだ」という自信が積み重なります。
比較しない声かけ
「友だちより早いね」という比較は、一見励ましに思えても「他者との優劣」で自己評価をする癖につながります。
代わりに「昨日より早く片付けられたね」と、過去の自分と比べる声かけを意識しましょう。こうした言葉が「自分の成長を喜ぶ」感覚を支えます。
否定ではなく肯定に言い換える
危険を止めるときにも「ダメ!」だけではなく、「ここなら安全にできるよ」と代替案を伝えると、禁止の言葉が少なくなり、園児も安心して行動できます。
声かけの実践事例
事例1:片付けの場面
園で片付けを嫌がる子に「早く片付けなさい」と言う代わりに、「片付けが終わったら次の遊びが始められるよ」と伝えると、子どもは前向きに動きやすくなります。その後「自分でやり切れたね」と認めると、達成感と自己肯定感が育ちます。
事例2:制作活動の場面
絵を描くのが苦手な子に「もっと丁寧に描きなさい」と言うと自信を失いますが、「好きな色を使ったね」「考えて選んだんだね」と声をかけると、自分の選択を認めてもらえたと感じます。
事例3:けんかの場面
友だちとけんかした後に「仲良くしなさい」ではなく、「気持ちを伝えられたんだね」「相手の気持ちも聞いてみようか」と声をかけると、対人関係の中で自分を大切にしながら相手も尊重する力が育ちます。
同僚との共有と園全体での取り組み
自己肯定感を育てる声かけは、保育士一人が頑張るだけでは継続が難しいものです。園全体で視点を共有することが大切です。
毎日のカンファレンスで「今日見取れた子どもの姿と声かけ」を話し合う
職員室に「声かけのヒント集」を掲示して活用する
新人保育士とベテラン保育士が一緒に振り返る
こうした工夫により、職員全体が同じ方向で子どもの育ちを支えることができます。
注意点とデメリット
自己肯定感を育てる声かけは保育現場にとって大切ですが、取り組み方を誤ると逆効果になることもあります。ここでは注意点とデメリットを整理しておきましょう。
褒めすぎの落とし穴
子どもの行動に対して、過剰に「すごいね」「えらいね」と褒めすぎると、園児は「褒められなければやらない」という状態になりかねません。自己肯定感を外部からの評価に依存させないために、「努力の過程」や「自分で工夫したこと」に焦点を当てるようにしましょう。
否定をゼロにする必要はない
「否定的な言葉を一切使わないようにしなければ」と考えると、保育士自身が苦しくなります。危険な場面では、短い言葉で即座に止める必要があります。その後で「どうすれば安全にできるか」を一緒に考えることで、否定から肯定的な学びへつなげられます。
子どもの個性を無視しない
同じ声かけでも、喜んで受け止める子もいれば、恥ずかしさから反発する子もいます。一律に「こうすれば自己肯定感が育つ」とは言えません。園児一人ひとりの反応を観察し、柔軟に声かけを工夫する必要があります。
保育士の負担感に注意
常に意識して声かけを工夫しようとすると、職員が疲れてしまうこともあります。完璧を目指すのではなく、「一日の中で1回でもプロセスを認める言葉を伝えられたらOK」と考えると続けやすくなります。
自己肯定感を育てるための園内環境の工夫
声かけと合わせて、園全体の環境も工夫すると効果が高まります。
制作物や作品を掲示し「努力の過程を見える化」する
異年齢の交流を取り入れ、子どもたちが「できることを伝える経験」を持てるようにする
職員室で「子どもの良い姿を共有する時間」を意識的に作る
声かけと環境が一体となって、子どもたちの自己肯定感を育ちやすくします。
実践を助ける関連書籍の紹介
実践を続ける中で「この関わりで合っているのか」「もっと良い方法はないか」と迷うこともあると思います。そんなときに役立つのが、理論と事例を学べる関連書籍です。ここでは特におすすめの4冊を紹介します。どれも教育・保育要領に沿った内容で、日々の実践や保護者さんへの説明に役立つものばかりです。
『10の姿プラス5・実践解説書』の活用
子どもたちの「10の姿」をどう保育実践に活かすかを具体的に知りたい先生におすすめな本です。教育・保育要領に示された「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を、豊富なカラー写真と実践事例でわかりやすく解説。園児の育ちを支える日々の保育に直結するヒントが満載です。新人からベテランまで現場で役立つ一冊です。
『10の姿で保育の質を高める本 』で学べる視点
保育実践の質を高めたい先生におすすめな本です。教育・保育要領に示される「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」をわかりやすく解説し、日々の保育にどう結びつけるか具体的に示しています。園児の育ちを支える視点を整理したい新人から、中堅・ベテランの先生まで活用できる一冊です。
『遊びや生活のなかで“10の姿"を育む保育 』で広がる事例
教育・保育要領に示された「10の姿」を実際の保育場面と結びつけて学べる実践書です。日常の遊びや生活の中でどのように子どもたちの育ちを支えるかを、豊富な事例と写真で具体的に解説。新人保育士から経験豊富な先生まで、保育の質を高めたい方に役立つ一冊です。
『幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿』による振り返り
園児の「思いやり」「協同性」「学びに向かう力」など、「幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿」をわかりやすく解説した一冊です。日々の保育の中でどんな場面を見取り、どう育ちを支えるのかを丁寧に示してくれるので、現場の実践にすぐ役立ちます。日々読み返したくなるので保育士の学び直しにもおすすめです。
どれも専門的な内容をやさしく解説しており、新しい視点で明日からの保育の質を高めたい方にぜひ読んでほしい本となっています。
よくある質問と回答
Q1. 自己肯定感を育てる声かけは忙しい現場で本当にできる?
→ すべての場面で意識するのは大変ですが、「一日の中で1回でも取り入れる」と考えると負担が減ります。例えば給食の時間に「昨日より一口多く食べられたね」と伝えるだけでも効果はあります。
Q2. 保護者さんとの連携はどうすればいい?
→ 園での声かけと家庭での言葉かけが一致すると、子どもの自己肯定感はさらに高まります。「今日は自分で靴を履けました。ご家庭でもできたらたくさん認めてあげてください」と伝えると、保護者さんも具体的に関われます。
Q3. 失敗したときの声かけは?
→ 「ダメだったね」で終わらせるのではなく、「チャレンジしたことが大事」「次はどうしたらいいと思う?」と問いかけてみましょう。失敗も成長の一部として受け止められるようになります。
Q4. 自己肯定感と甘やかしはどう違う?
→ 甘やかしは「子どもの要求をそのまま受け入れること」、自己肯定感を育てるのは「努力や気持ちを認め、次の挑戦を支えること」です。違いを理解すると声かけの方向性が見えてきます。
日々の保育で試してみたい工夫
工夫1:声かけの共有ノートを作る
職員同士で「今日こんな声かけをして子どもが嬉しそうだった」という事例を共有すると、チーム全体で意識が高まります。新人保育士も真似しやすくなり、園全体の保育の質が向上します。
工夫2:子どもの小さな成長を掲示する
「自分で片付けられた」「友だちにありがとうと言えた」などの小さな成功を写真やコメントで掲示すると、子どもたちは自分の姿を誇らしく感じ、自己肯定感を深めていきます。
工夫3:保護者さんへ伝える工夫
連絡帳や送迎時に「今日はできたこと」を一言添えるだけで、保護者さんも子どもの成長を実感できます。園と家庭がつながることで、自己肯定感の育ちは一層確かなものになります。
工夫4:毎日の振り返り
「今日、どんな声かけができたか」を職員会議で短く振り返る時間を設けると、継続的に取り組めます。少しずつでも積み重ねることで園の文化になっていきます。
まとめ
自己肯定感を育てる声かけは、子どもたちが安心して挑戦できる環境を作り出します。大げさな言葉ではなく、日常の中の小さな成長を認めるだけで十分です。
声かけの工夫は一人で抱え込むのではなく、同僚や保護者さんと共有することで持続可能になります。今日からまず一つ、自分ができそうな声かけを意識してみてください。その積み重ねが、園児の「育ちを支える」力になります。