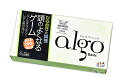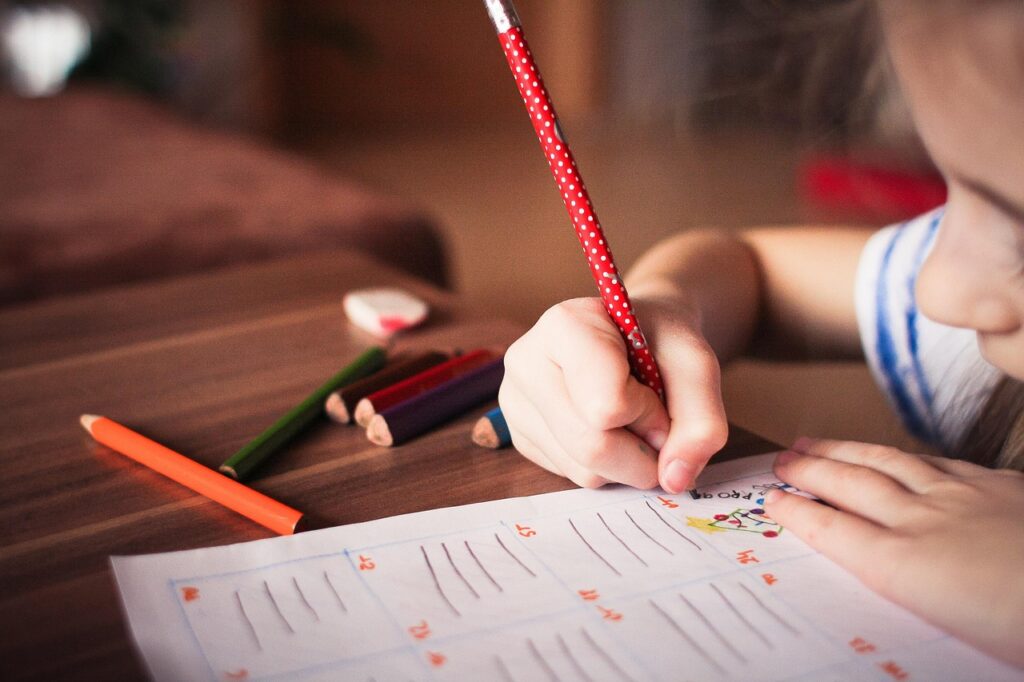
「うちの子、すぐに気が散ってしまって…」「ひとつのことを続けられないんです」
そんな悩みを抱えるお父さん・お母さんは少なくありません。
絵本を読んでいても数分で他の遊びに移ってしまったり、パズルを始めても途中でやめてしまったり。
「集中力が足りないのでは」と心配になる気持ち、よくわかります。
でも実は、子どもの集中力は「生まれつきの性格」ではなく、環境と関わり方で育つ力です。
大人がほんの少し工夫するだけで、お子さんは驚くほど集中できるようになります。
幼児教育の知見をもとに見ると、子どもの集中は「夢中になる時間」から生まれます。
何かに熱中し、試行錯誤しながら取り組む体験が、集中力の土台をつくっていくのです。
この記事では、子どもの集中力が育つ仕組みや、家庭でできる環境づくり、そして日常の中での工夫を紹介します。
さらに後半では、遊びながら集中力を伸ばせる知育玩具の選び方や使い方もご紹介します。
焦らず、楽しく、お子さんの「育ちを支える」ヒントを一緒に見ていきましょう。
集中力とは?その正体を知ることから始めよう
集中力は「性格」ではなく「経験」で育つ
多くの親御さんが、「うちの子は集中力がない」と感じる場面は多いもの。
けれど、それは性格の問題ではありません。集中力は「繰り返しの経験」で鍛えられる力です。
発達心理学の視点では、集中力とは「一つの対象に注意を向け続ける力」と「必要な情報を選び取る力」の組み合わせです。
この2つの力は、遊びや生活の中で少しずつ発達していきます。
例えば、積み木を積む遊びでは「どこまで高くできるかな?」という探究心が集中を生みます。
そして倒れてももう一度やってみようとする過程が、「やり抜く力」を育てていくのです。
大切なのは、「集中させよう」とするよりも、「集中できる環境を整える」こと。
集中力は、“育てるもの”なのです。
幼児期〜小学校期の集中時間の目安
お子さんの集中時間は、年齢によって自然に変わっていきます。
心理学の研究では、平均的な集中時間は以下の通りです。
3歳前後:約3〜5分
4〜5歳:約10〜15分
小学校低学年:約20〜30分
小学校高学年:約40分前後
つまり、「すぐ飽きてしまう」「集中が切れる」のは、発達の段階として自然なことです。
大人のように30分以上続けて集中するのは、まだ難しい時期。
「短い集中を何度も繰り返す」ことが、持続力を伸ばす練習になります。
お父さんやお母さんが「今の集中でもいいんだ」と受け止めることで、お子さんの安心感はぐっと高まります。
遊びの中で集中が生まれる理由
子どもは「好きなこと」や「やってみたい」と思えることに出会ったとき、自然と集中します。
それは“義務”ではなく、“内側からの興味”によって生まれるからです。
幼児教育の現場でも、子どもが夢中になるのは「評価される活動」ではなく、「自分で考えて工夫できる遊び」です。
ブロック、粘土、ままごと、絵を描く——いずれも集中力を鍛える立派な教材です。
「静かに座っていられるか」ではなく、
「どんな場面で夢中になっているか」を見取ることが、集中力を支える第一歩です。
「夢中になれる時間」をどう見取るか
たとえば、ブロックで塔を作る姿、絵を描く手の動き、ままごとの世界を広げる語り。
これらはすべて、集中の姿です。
「集中=勉強」と考える必要はありません。
小さな成功体験を積み重ねる中で、脳は「もう少しやってみよう」と前向きなモードになります。
この繰り返しが、やがて学びの集中へとつながっていくのです。
お父さん・お母さんは、結果を急がずに**“夢中の時間”を一緒に味わうこと**を意識してみてください。
集中力が続かない子どもの特徴と原因
環境の刺激が多すぎる
お子さんの集中が続かないとき、まず見直したいのが「環境」です。
テレビやスマートフォン、ゲーム、カラフルなおもちゃ——どれも魅力的ですが、刺激が強すぎると、注意が分散しやすくなります。
特に映像の切り替わりが速い動画やアニメは、脳が「次の刺激を求める」状態に慣れてしまいます。
その結果、静かな活動(ブロック・パズル・お絵かきなど)に取り組む時間が短くなる傾向があります。
「刺激を減らす=何もない空間にする」という意味ではありません。
ポイントは、“選ぶ自由”を残したうえで、落ち着ける空間を整えることです。
たとえば、
テレビの音を消して、静かに遊べる時間を1日20分つくる
おもちゃを出しっぱなしにせず、「今日はこれで遊ぼう」と一緒に選ぶ
こうした小さな工夫が、集中しやすい環境をつくります。
睡眠や生活リズムの乱れ
集中力は脳の働きと密接に関わっています。
十分な睡眠をとっていないと、脳が情報を整理する時間が不足し、注意の持続が難しくなります。
特に幼児期は、夜更かしや不規則な食事時間が続くと、日中の活動意欲が下がる傾向があります。
「朝日を浴びて体を起こす」「決まった時間に寝る」といった生活のリズムを整えることが、集中の土台になります。
ある調査では、睡眠時間が9時間未満の子どもは、10時間以上眠る子よりも注意の持続力が平均で25%低下すると報告されています。
集中力を伸ばす前に、「しっかり眠れているか」を見直してみるのも大切です。
親の声かけがプレッシャーになることも
「もう少し集中して」「最後までやってみよう」——つい言いたくなる言葉ですが、実は逆効果になることもあります。
叱られる経験が増えると、子どもは「どうせできない」と感じやすくなり、挑戦への意欲が下がります。
もちろん、励ますつもりでかけた言葉でも、受け取り方はさまざまです。
大切なのは、「できた・できない」ではなく、「どう工夫したか」「どう感じたか」に目を向けることです。
たとえば、
「途中であきらめずにがんばってたね」
「前より長く続けられたね」
といった言葉は、努力の過程を認めることにつながります。
結果ではなく挑戦する姿を見取ることが、集中力を支える声かけのコツです。
発達の個性による集中の違い
集中力の形は、子どもによって違います。
じっと座って取り組む子もいれば、体を動かしながら考える子もいます。
「落ち着きがない」と感じる行動も、実は「体を動かすことで集中している」場合があります。
幼児教育の現場では、動きながら取り組むことも“集中”と捉えます。
大人が「こうあるべき」と決めつけるのではなく、お子さんなりの集中の形を尊重することが大切です。
それを理解して関わることで、安心して取り組む力が育ちます。
家庭でできる集中力を育てる環境づくり
「静かな場所」より「安心できる空間」をつくる
集中に必要なのは、静けさではなく「安心感」です。
テレビや人の声が聞こえない場所でなくても、「ここなら落ち着ける」と感じるスペースがあれば十分です。
たとえば、リビングの一角に小さな机を置き、好きな絵本やパズルを並べておく。
その場所にお気に入りのぬいぐるみを置くだけでも、子どもは安心して取り組めるようになります。
お父さん・お母さんが「一緒にやってみよう」と声をかけて隣に座ると、より集中しやすい環境になります。
時間ではなく“やりきる感覚”を大切にする
「10分間座っていようね」と時間で区切るより、「このパズルを完成させよう」と目的を共有するほうが集中が続きます。
やりきる経験が“達成感”を生み、その達成感が次の集中へとつながります。
時間の長さではなく、「自分で最後までできた」という手応えを積み重ねることが、集中力の育ちを支えます。
親の関わり方で変わる!声かけの工夫
「上手だね」よりも「がんばってたね」と伝えるだけで、子どもの心は大きく動きます。
結果を評価するよりも、過程を見守る言葉を意識しましょう。
また、集中している最中は話しかけすぎないこともポイントです。
親が静かに見守ることで、「自分のペースで考えていい」と感じ、集中が深まります。
日常の遊びが「集中の土台」をつくる
実は、特別な教材がなくても、集中力は日常の遊びで十分に育ちます。
料理の手伝い、洗濯物をたたむ、絵を描く——いずれも集中の練習です。
子どもは「自分の役割がある」と感じることで、やる気と集中を引き出します。
家庭の中に“挑戦できる小さな場面”をつくっていくことが、最大の環境づくりです。
集中力を楽しく伸ばす!知育玩具の活用法
遊びながら考える経験が“集中の持続”を育てる
「遊んでばかりでいいの?」と心配になる親御さんもいますが、実は遊びこそが最高の学びです。
子どもが集中するのは、「やらされる勉強」よりも「自分でやってみたい」と感じる活動のとき。
知育玩具は、まさにその“自発的な集中”を引き出してくれる道具です。
たとえばブロック遊び。
何を作るかを自分で考え、試し、失敗して、もう一度やり直す。
この繰り返しが、集中力だけでなく論理的思考力や問題解決力を育てていきます。
幼児教育の知見でも、「考えながら手を動かす」活動は、脳の前頭前野(集中・計画・判断をつかさどる部分)を刺激するといわれています。
つまり、遊びを通して自然に集中力が育っていくのです。
年齢別に見るおすすめの知育玩具
子どもの発達段階に合わせて、遊び方や興味は大きく変化します。
お子さんの年齢や性格に合った玩具を選ぶことが、集中を支えるカギになります。
3〜4歳ごろ
この時期は、手先を使う遊びで集中力を育てるのがおすすめ。
ブロック(レゴデュプロなど)
型はめパズル
積み木やひも通し
「できた!」という成功体験をくり返すことで、自信が育ちます。
5〜6歳ごろ
少し複雑なルールや手順が理解できるようになる時期。
バランスゲーム
マグネットブロック
知育ボードゲーム
考えながら試行錯誤する経験が、集中の持続につながります。
小学生以降
この頃になると、「完成させたい」「もっと上手になりたい」という意欲が高まります。
プログラミングトイ(レゴ®エデュケーション SPIKE™など)
迷路パズル
科学実験キット
遊びながら“探究心”を満たすことで、学びへの集中が自然と深まります。
親子で一緒に“集中の楽しさ”を共有しよう
知育玩具を与えるだけでは、集中力は育ちません。
大切なのは、「一緒に楽しむ時間」です。
たとえば、
「どっちが高く積めるかやってみよう!」
「次はどんな形にしてみる?」
と声をかけながら、親も一緒に夢中になることで、お子さんの集中時間は格段に伸びます。
子どもは「見てもらえている」と感じると、挑戦する意欲が増します。
集中の持続には、「安心」と「共感」が欠かせません。
また、知育玩具は“長く遊べるもの”を選ぶのもポイントです。
単なる一時的なブームで終わらず、年齢や発達に応じて遊び方が変化していくものを選びましょう。
1.テンヨー 『脳ブロック』
手のひらサイズから始まる“遊びの旅”。テンヨーの知育ブロックシリーズは、形や色を自分で選びながら創り出す楽しさが詰まっています。小さなお子さんが「やってみたい!」と手を伸ばす瞬間が、集中力や想像力の育ちを後押しします。親御さんも一緒に遊ぶことで、笑顔と達成感を共有できるのも魅力。家庭での遊び時間を、子どもの“育ちを支える”時間に変えてみませんか?
2.カワダ 『ナンスピ』
「遊びながら夢中になれる」その瞬間が、集中力を育てる大切な出発点です。KAWADAのこのボードゲームは、数字カードやライトの順番を記憶してチャレンジする3つのモードを備え、遊びながら集中力・注意力・記憶力を鍛えられます。対象年齢6歳以上、コンパクトなサイズなのでご家庭のリビングでも楽しめ、お子さんと一緒に「できた!」という達成感を分かち合えるのも魅力。家庭時間を、育ちを支える“遊び時間”に変えてみませんか。
3.マテルゲーム ブロックス トライゴン
この知育ボードゲームは、「遊びながら賢くなる」家庭時間を実現します。2〜4人で遊べる仕様で、対象年齢7歳以上。三角形のピースを交互にボードに配置し、最終的に多くのマスを埋められたプレイヤーが勝利というルールで、視覚-空間能力や計画力、集中力を育てる工夫が詰まっています。遊びが終わったら「どこが難しかった?どう変えた?」と話すことで、お子さんの“考える力”を育ちを支える時間にもなります。
4.アルゴ ベーシック (頭のよくなるゲーム)
数学と論理的思考を楽しく伸ばせる一冊です。カードを使って「何が隠れているの?」と推理しながら遊ぶ教材で、遊びの中に集中力や分析力が自然と育まれます。お子さんが「気になる!」「もう一回やってみたい!」という瞬間を増やせるのも魅力。お父さん・お母さんがそばで声をかけながら、「今日の発見はね」と子どもの育ちを支える時間になる一冊です。
5.子どもの「集中力」を育てる聞くトレ 聞く・見る力を改善する特別支援教育 / 上嶋 惠 著
日常の子育てにひと工夫を加えたいと感じているお父さん・お母さんへ。この一冊は、発達心理学と現場で培われた知見をやさしく紐解いており、お子さんの「なんでこうするの?」という行動に対して、理解と安心をもたらしてくれます。遊びやコミュニケーションを通じて『集中力・意欲・社会性』を育てる具体的なヒントが満載。家庭での子どもの育ちを支えるための、心強いパートナーとなる一冊です。
よくある質問(Q&A形式)
Q. すぐ飽きてしまうのは集中力がないから?
A. 飽きっぽく見えても、実は「興味の方向が変わっただけ」のことが多いです。
同じおもちゃでも遊び方を変えるだけで、再び集中が戻ることがあります。
「今日はどんな遊び方ができるかな?」と親が提案してあげるのも効果的です。
Q. 兄弟で集中力に差があるのはなぜ?
A. 集中のスタイルは子どもによって違います。
上の子が静かに座って遊ぶタイプでも、下の子は動きながら集中するタイプかもしれません。
「同じにしよう」とするより、それぞれの集中の形を見取ってあげることが大切です。
Q. ゲームや動画も集中力を鍛えられますか?
A. 一時的には集中して見ていますが、受け身の刺激なので“持続する集中力”とは少し異なります。
ただし、視聴後に「どこが面白かった?」「どう思った?」と対話を入れることで、考える集中に変えることは可能です。
Q. 知育玩具は高価なものを買った方がいい?
A. 価格よりも「継続して遊べるか」が大事です。
子どもが自分で工夫したり、成長に合わせて遊び方を変えられるおもちゃが理想です。
たとえば、ブロックや積み木のような“自由度の高い玩具”は長く使えるためおすすめです。
知育玩具は、子どもの集中力を伸ばすだけでなく、親子のコミュニケーションを深めるツールでもあります。
遊びながらお子さんの“夢中になる姿”を見取り、成長の小さな変化を一緒に喜んでいきましょう。
注意点とデメリットも知っておこう
無理に集中させようとすると逆効果
「もう少し頑張って!」「最後まで座って!」——つい言ってしまう言葉ですが、これは集中力を削ぐ原因になることがあります。
集中力は“コントロールできる筋肉”ではなく、心のエネルギーのようなもの。
大人でも気分がのらない日があるように、子どもも「今日は集中できない日」があって当然です。
幼児教育の知見でも、集中を強制するより「自然に夢中になれる活動」を増やすほうが、結果的に集中が長続きすると言われています。
無理に引き戻すより、「今日はここまででもいいよ」と区切りをつけるほうが、次への意欲につながります。
「静かにしている=集中している」ではない
お子さんが静かにしていると、つい「集中している」と思ってしまいがちです。
でも、動きながら考えたり、話しながら取り組んだりすることも立派な集中です。
体を動かしながら遊ぶのが好きな子は、「動きながら考えるタイプ」かもしれません。
大切なのは、“姿勢”ではなく“意識の向き”を見取ることです。
「何に心が向いているのか」「どんなことに夢中になっているのか」を丁寧に見守ることで、お子さんの本当の集中力が見えてきます。
親の期待がプレッシャーになることも
「集中できるようになってほしい」という気持ちは、お父さん・お母さんの愛情そのもの。
でも、過度な期待はプレッシャーになることもあります。
「なんでできないの?」「さっきはできたのに」と言われ続けると、子どもは「どうせ失敗する」と感じてしまいます。
心理学では、こうした状態を“自己効力感の低下”と呼び、挑戦する意欲を下げる要因になるとされています。
そんなときは、できたことを一緒に振り返るのがおすすめです。
「ここまで頑張ったね」「前より少し長く続けられたね」といった言葉が、子どもの自信を取り戻します。
知育玩具も“与えっぱなし”では育たない
知育玩具は、使い方次第でお子さんの集中力をぐんと引き出します。
ただし、“買って渡すだけ”では効果が半減してしまいます。
大切なのは、「一緒に楽しむこと」「見守ること」「話を聞くこと」。
「どんなふうに作ったの?」「ここはどうやったの?」と興味を示すことで、子どもは「見てもらえている」と感じ、もっと頑張りたくなります。
知育玩具は、“親子の関係を育てるツール”としても活用できるのです。
まとめ
集中力は、生まれつきの才能ではなく、日々の環境と関わりの中で育つ力です。
お父さんやお母さんが少し意識を変えるだけで、お子さんの「夢中になる時間」はぐっと増えていきます。
家庭の中でできることは、特別なことではありません。
安心できる場所をつくる、褒め方を工夫する、そして一緒に楽しむ——その積み重ねが、お子さんの育ちを支える大きな力になります。
これから試してみたい工夫
安心できる“集中スペース”をつくる
リビングの一角など、落ち着ける場所をお子さんと一緒につくりましょう。結果ではなく「過程」をほめる
「よく考えたね」「頑張って工夫してたね」と、努力を認める言葉が集中力を支えます。“時間”より“やりきる感覚”を大切にする
10分続けるよりも、「完成させた」「できた」という手応えを大事にしましょう。知育玩具を通して親子で“夢中”を共有する
ブロックやパズルなど、一緒に遊ぶ時間を通して「集中の楽しさ」を感じてみてください。
お子さんの集中力は、焦らず、丁寧に育てていくものです。
日々の中で「今日はここまでできたね」と小さな成長を一緒に喜びながら、
お子さんの“育ちを支える家庭時間”を大切にしてほしいなと思います。