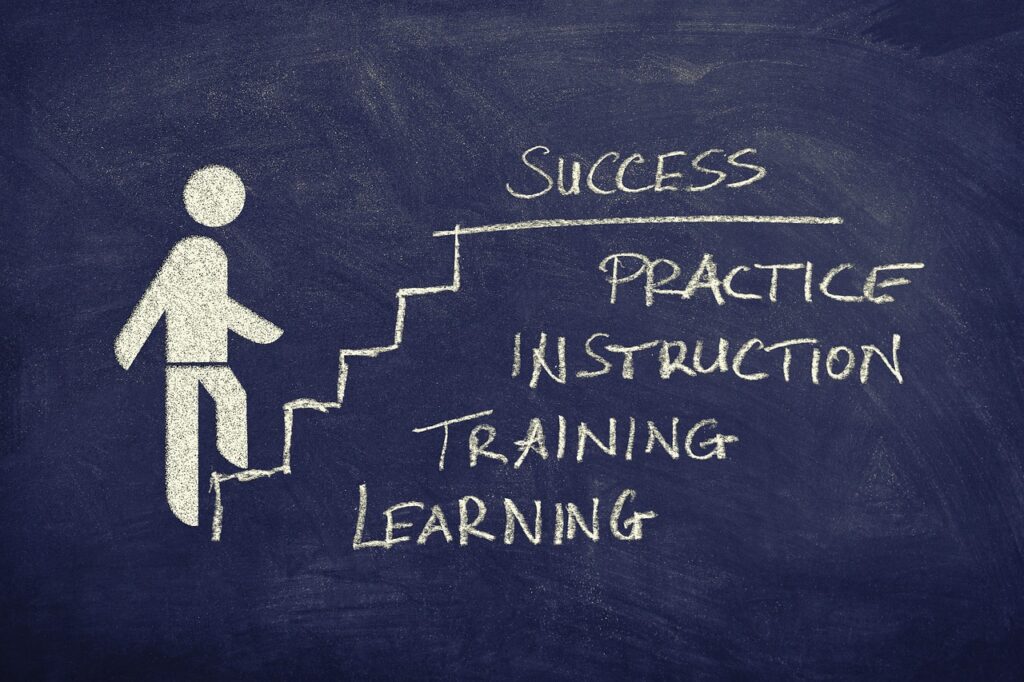
「カリキュラム・マネジメント」という言葉を、園内研修や教育・保育要領の資料で目にしたことがある方も多いでしょう。けれども現場の保育教諭からは「難しそう」「学校の話では?」という声もよく聞かれます。私自身も園長先生に「これからはカリキュラム・マネジメントを意識して」と言われて正直ピンと来ませんでした。
しかし経験を重ねる中で気づいたのは、カリキュラム・マネジメントは特別な活動ではなく、私たちが日々行っている「計画→実践→振り返り→改善」の流れそのものだということです。この記事では、その意味と園内での具体的な取り組み方を、事例を交えながら分かりやすく解説します。
カリキュラム・マネジメントとは?
定義と背景
カリキュラム・マネジメントとは、教育・保育要領で示された「計画・実践・評価・改善」を循環させ、子どもの育ちをより豊かにする取り組みのことです。もともとは学校教育分野で使われていた用語ですが、2018年改訂の教育・保育要領で幼児教育にも導入されました。
ポイントは、個々の活動や行事を単発で終わらせず、全体の流れとしてつなげること。つまり「今年度のカリキュラムを園全体でどう設計するか」「実践をどう評価して次に生かすか」を考える仕組みです。
「計画・実践・評価・改善」の循環サイクル
多くの方が知っている「PDCAサイクル」と似ていますが、幼児教育におけるカリキュラム・マネジメントは、子どもの姿を基点にする点が大きな特徴です。
計画(Plan):子どもの発達や興味を踏まえて、年間・月間の指導計画を立てる
実践(Do):実際に保育を行い、子どもと関わる
評価(Check):子どもの姿を観察し、計画通りかどうかを見直す
改善(Action):評価をもとに次の計画に反映する
園内におけるカリキュラム・マネジメントの流れ
計画(Plan)
例えば、年間指導計画で「自然に親しむ経験を通して命の大切さを学ぶ」と設定したとします。そこから月案では「5月に野菜を植える」「7月に収穫する」と具体化し、週案や日案に落とし込む。
ポイント:ねらいは子どもの発達段階や興味に即して立てること。「去年と同じだから」ではなく、その年の子どもに合わせて柔軟に設定することが大切です。
実践(Do)
計画した内容を保育現場で実際に行います。ただし「計画通りに進める」ことが目的ではなく、子どもの反応を見ながら調整する柔軟さが求められます。
私が担当した4歳児クラスでは、夏に「ひまわりの観察」を計画しましたが、子どもたちは水やりよりも「虫探し」に夢中になりました。そこで計画を変更し、「虫の観察」も取り入れた結果、自然への関心がより広がりました。
評価(Check)
保育終了後や週末に、子どもの姿を振り返ります。「活動を楽しんでいたか」「ねらいに近づけたか」を保育者同士で話し合いましょう。
例:
Aくんは虫を怖がっていたが、友達の声かけで観察に参加できた。
Bちゃんは野菜の成長に気づき、毎日水やりを続けていた。
ポイント:評価は「できた・できない」ではなく、子どもの姿から「次の課題や発展」を考えることです。
改善(Action)
評価をもとに次の保育を調整します。「虫探しが人気だったから、次回は観察用の虫かごを準備しよう」「水やり当番を決めて責任感を育てよう」といった改善です。
園全体では、週案や月案を振り返り、職員会議や園内研修で共有することも重要です。
現場でよくある課題と解決のヒント
評価が形だけになってしまう
「○○活動を実施、子どもは楽しんでいた」で終わってしまいがちです。
→ 子どもの具体的なエピソードを書くことが大切。短い記録でも「○○ちゃんが自ら片付けを始めた」など、次につながる気づきになります。
改善が次に生かされない
記録しても共有がなければ改善は進みません。
→ 園内で「評価を持ち寄る時間」を定期的に設け、全員で共有する仕組みを作りましょう。
時間が足りない
「振り返る余裕がない」という声もあります。
→ ICTを活用して記録を簡略化したり、写真を活用して振り返るなど、効率的な方法を取り入れると継続しやすいです。
みんな最初は難しい
カリキュラム・マネジメントと聞くと「なんだか専門的で難しい」と感じるのは自然なことです。私も新人の頃、週案を書くだけで精一杯で、改善や評価まで手が回りませんでした。
でも先輩に「ほんの一言でいいから、気づいたことを書いておけば次につながるよ」と言われ、少しずつ記録を残す習慣がつきました。大切なのは完璧を目指さず、小さな一歩から始めることです。
今日からできる一歩
1日の保育を振り返り、子どもの姿を1つだけメモする
→ 例:「給食後、友達と協力して片付けていた」。週1回、チームで「評価の共有時間」を持つ
→ 5分でもよいので、子どもの姿を言葉にして出し合う。改善点を1つだけ次の保育に取り入れる
→ 「おもちゃの片付けが難しそうだった → 次回は片付け場所の写真を貼る」など。
まとめ
カリキュラム・マネジメントは難しい特別なものではなく、保育教諭が日々の実践で自然に行っている「計画・実践・評価・改善」の流れそのものです。重要なのは、それを園全体で意識的に行い、次の保育に生かすこと。
小さな一歩で構いません。今日から「子どもの姿を一言メモする」ことから始めてみましょう。その積み重ねが園全体の保育の質を高め、子ども一人ひとりの育ちを豊かにしていきます。
次の週案を書くときに、ぜひ「評価」と「改善」をセットで考えてみたいですね。
こちらもCHECK
-

【効率化◎】保育で役立つ!事務作業や製作がはかどるおすすめ便利グッズ12選
時間が足りない保育現場で“効率化”がどれほど重要か。 保育園での製作や事務の業務は、準備・切り出し・補助用具の整理など、意外と手間がかかり、気づけば残業や持ち帰り作業になりがちですよね。「準備が追いつ ...
続きを見る
