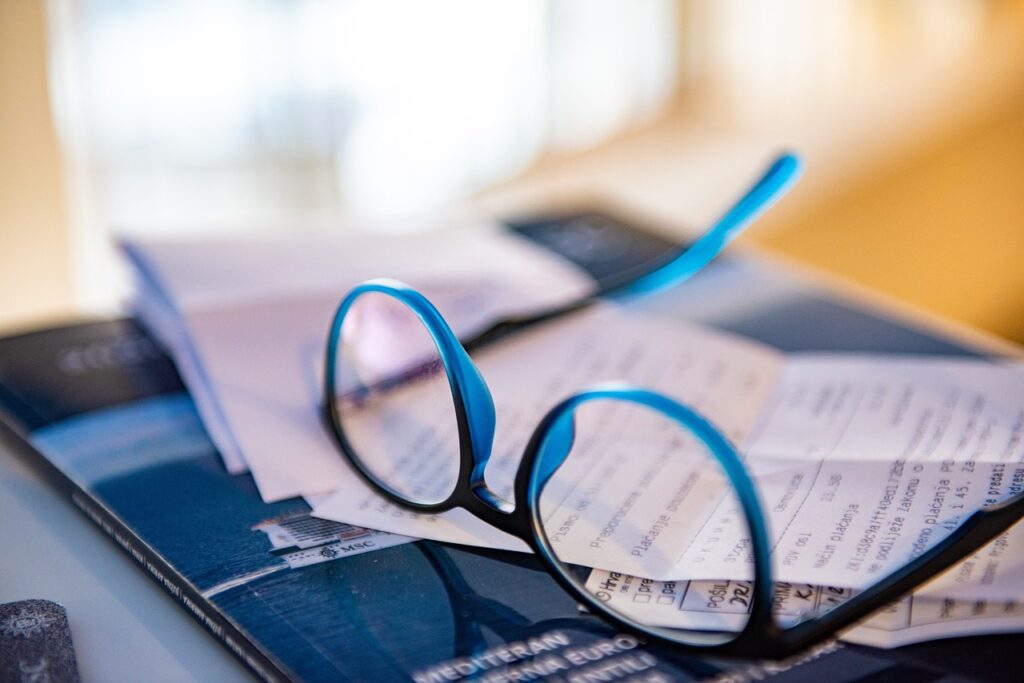
社会福祉法人が運営する認定こども園や保育園では、毎日の子どもたちの生活を支えるために多くの会計処理が発生します。保育料や給食費、行政からの補助金や助成金、そして園舎や備品にかかる費用。これらを正しく仕訳して帳簿に記録することは、法人の信頼性を守る上で欠かせません。
しかし現場では「どの帳簿を必ず整えておくべきなのかが分からない」「監査で毎回修正を求められている」「補助金の処理に時間を取られすぎている」といった悩みが尽きません。園長や理事長も、保育や経営判断に加えて帳簿を確認しなければならず、会計担当にとっても責任の重い仕事です。
この記事では、社会福祉法人の認定こども園・保育園で必要となる帳簿を整理し、会計担当が押さえるべき基本と実務の流れを紹介します。やや専門的な内容も噛み砕いて説明しますので、会計初心者の方でも理解しやすい内容になっています。
社会福祉法人会計の特徴と帳簿の役割
一般企業会計との違いと説明責任の重要性
まず理解しておきたいのは、社会福祉法人の会計は株式会社などの一般企業会計とは根本的に目的が異なるという点です。一般企業は利益を算出するために損益計算書を中心に据えますが、社会福祉法人会計では「お金がどこから入り、どのように使われたか」を明らかにすることが重視されます。
そのため、資金収支計算書や事業活動計算書の作成が必須となり、透明性と説明責任を果たすことが求められます。行政からの補助金や利用者からの保育料は、公共性の高い資金であるため、一つひとつの帳簿が「適切に使われている証拠」となるのです。
帳簿が果たす透明性と信頼性の確保
帳簿は単なる記録ではなく、法人運営に対する信頼性を支える重要なツールです。帳簿がきちんと整備されていないと、行政からの指摘や補助金の返還を求められるリスクが高まります。
また、監査の際に帳簿が不完全だと、園全体の信用問題にも直結します。日々の小さな支出であっても、正しく帳簿に反映することが大切です。
会計担当がまず理解すべき基本視点
会計担当が最初に押さえるべきポイントは「正確さ」と「一貫性」です。同じ支出でも担当者ごとに勘定科目が異なるようでは、法人全体の数字にズレが生じます。日常の取引を記録する段階からルールを統一し、誰が見ても同じ判断で仕訳されている状態を作ることが欠かせません。
認定こども園・保育園で必要となる主な帳簿
現金出納帳・預金出納帳
最も基本的な帳簿が現金出納帳と預金出納帳です。小口現金の管理や銀行口座の入出金を正確に記録しておくことで、日常的な不一致を防ぎます。少額の支出だからといって記録を怠ると、後で大きなズレを生む原因となるので注意が必要です。
補助金収支簿・助成金管理簿
社会福祉法人に特徴的なのが補助金関連の帳簿です。行政から交付される補助金や助成金は、交付決定額・精算額・返還額を正しく管理する必要があります。仕訳を誤ると返還や修正を求められることがあり、園の信用を損なう恐れがあります。
資金収支計算書・事業活動計算書
資金収支計算書は、お金の流れを包括的に示す帳簿で、資金の使途を正確に把握できます。事業活動計算書は教育・保育事業、延長保育、給食などの区分ごとの収支を明確にする帳簿です。これらは法人の経営状況を見える化する役割を担い、理事長や園長が経営判断を行う上でも欠かせません。
固定資産台帳と減価償却の管理
園舎や遊具、園バスやパソコンなど、長期にわたって使用する資産は固定資産台帳で管理します。取得価額、購入日、耐用年数を記録し、減価償却を適切に処理することで、資産の現状を正しく把握できます。これを怠ると将来的な修繕や更新の計画に支障をきたすため、見落とさないよう注意が必要です。
会計担当が直面しやすい課題
区分経理の複雑さと仕訳の混乱
社会福祉法人会計において特に負担が大きいのが区分経理です。本園と分園の区別、教育・保育、延長保育、給食などの事業ごとの区分。これを誤ると監査で必ず指摘されます。Excelで集計している園もありますが、仕訳数が多くなると処理に時間がかかり、人的ミスの原因になります。
補助金や助成金処理の煩雑さ
補助金の処理は常に会計担当を悩ませます。年度ごとに制度が変わることもあり、最新のルールに沿った仕訳が必要です。交付から精算、場合によっては返還に至るまで追跡管理が必要で、ひとつの誤りが大きな影響を及ぼします。
監査や行政報告での資料準備の負担
年度末の監査や行政報告では、大量の帳簿や証憑を確認されます。普段から整理ができていないと、その時期だけ膨大な時間を割かざるを得ません。会計担当の中には「監査前は胃が痛くなる」という方も少なくないのが実情です。
帳簿管理を正しく行うための基本ステップ
日常の取引を正確に仕訳する習慣
帳簿管理を正しく行うための第一歩は、日常の取引を漏れなく正しく仕訳する習慣です。少額の支出や臨時的な収入でも、その都度記録していくことが重要です。例えば「職員研修用の資料を購入した」場合、勘定科目を教育訓練費として仕訳し、領収書を添付します。小さな処理の積み重ねが、決算期の混乱を防ぐことにつながります。
帳簿と証憑を常に突合する重要性
会計監査や行政報告では、帳簿の数字と証憑の一致が求められます。日々の段階で領収書や請求書を帳簿と突合し、保管する習慣をつけておけば、年度末にまとめて探す手間が省けます。「この支出の証憑はどこ?」と探し回る時間は、会計担当にとって大きなストレスです。
職員間でルールを統一して属人化を防ぐ
帳簿管理でよくある課題は、担当者ごとに処理の仕方が違ってしまうことです。ある人は「消耗品費」で仕訳し、別の人は「備品費」に計上してしまう。このズレは後々の集計を難しくします。園全体で仕訳のルールを統一し、マニュアルを整備することで、誰が担当しても同じ精度で処理ができる体制を作ることが大切です。
注意点と押さえておきたいリスク
帳簿の不備による行政からの指摘や補助金返還
帳簿の不備があると、行政から修正を求められたり、最悪の場合補助金の返還を命じられることがあります。たとえば、補助金を人件費ではなく設備費に計上してしまった場合、監査で誤りを指摘され、返還に至るケースもあります。こうしたリスクを防ぐために、帳簿の正確性は常に意識しなければなりません。
区分経理が不十分な場合の監査での影響
区分経理が曖昧だと、監査で「本園と分園の支出が混在している」「教育事業と延長保育が分かれていない」といった指摘を受けます。監査対応に追われると、会計担当だけでなく園長や理事長まで時間を取られることになります。区分経理は面倒でも、日常的に徹底しておくことが園全体の負担を減らす近道です。
担当者任せにせず法人全体で共有すべき理由
帳簿管理を一人の担当者に任せきりにすると、その人が休職や退職をしたときに大きなリスクになります。会計は法人全体の責任として取り組む姿勢が必要です。理事長や園長が帳簿の流れを理解しているだけでも、担当者の安心感につながります。
よくある質問(FAQ)
Q1. 帳簿はどのくらいの期間保存しなければなりませんか?
法律上、原則として帳簿や証憑は7年間保存する必要があります。固定資産に関する記録など一部は10年間の保存が求められる場合もあります。保存期間を守らないと監査で指摘される可能性があるため、早めに保存ルールを法人内で決めておくことが安心です。
Q2. 帳簿はすべて紙で残す必要がありますか?
必ずしも紙で残す必要はありません。近年では電子保存も認められており、検索性や保管のしやすさを考えるとデジタル管理が推奨されます。ただし、保存期間や形式については法令に従う必要があります。
Q3. 区分経理はどの程度細かく行うべきですか?
基本は本園・分園や事業ごとに分けることが求められます。特に教育・保育、延長保育、給食などは別区分で管理するのが原則です。細かすぎても実務が煩雑になりますが、監査で説明できるレベルで整理しておくことが必要です。
Q4. 監査で特に確認されやすい帳簿はどれですか?
補助金関連の帳簿、資金収支計算書、事業活動計算書は特に重点的に確認されます。これらは補助金の適切な利用状況や、事業運営の健全性を判断するための重要資料となるからです。
実際にあった導入事例と改善の効果
監査準備がスムーズになった園
ある認定こども園では、監査の時期になると毎回数日間かけて資料を探し、帳簿と突き合わせをしていました。担当者も園長も疲弊し、職員全体に緊張感が走っていました。
そこで帳簿を日常的に整理し、証憑も逐一ファイリングする体制を作った結果、監査準備が従来の半分の時間で完了するようになりました。担当者は「監査前に胃が痛くなることが減った」と話しており、法人全体の心理的な負担も軽くなったのです。
区分経理を徹底して指摘がなくなった園
別の園では、延長保育や給食費といった事業区分の仕訳が不十分で、毎年監査で「区分が混在している」と指摘を受けていました。そこで本園・分園、事業ごとに明確にルールを定め、職員全員で共有しました。その結果、監査での指摘がゼロに。園長は「数字の透明性が高まったことで、理事会での説明もスムーズになった」と話しています。
帳簿管理の意識が法人全体に根付いた園
帳簿管理を一人の担当に任せきりにしていた園では、担当者の休職で業務がストップしてしまったことがありました。その経験を機に、理事長や園長も会計の基本を理解し、法人全体で共有する文化を作りました。結果的に「担当が変わっても混乱しない」体制が整い、安心感が広がったのです。
さらに帳簿管理の業務負担を削減したい方へ
ここまで、社会福祉法人の認定こども園・保育園で必要となる帳簿や、会計担当が押さえておくべき基本について説明してきました。ただ、多くの方が「もっと効率化したい」「日常の実務の流れを具体的に知りたい」と感じているのではないでしょうか。
そんな方におすすめしたいのが、こちらの記事です。
こちらもCHECK
-

【社会福祉法人会計】保育園、認定こども園におすすめ!クラウド会計ソフトで初心者でも安心して会計の業務負担を削減しよう
社会福祉法人が運営する保育園や認定こども園では、日々の保育に加えて「会計」という大きな仕事があります。子どもたちのこと、職員のこと、保護者対応、行政とのやり取り…。そのうえで、仕分けや帳簿、補助金処理 ...
続きを見る
まとめ
社会福祉法人の認定こども園や保育園で必要となる帳簿は、現金出納帳、預金出納帳、補助金収支簿、資金収支計算書、事業活動計算書、固定資産台帳など多岐にわたります。これらを正しく整備しなければ、行政からの指摘や補助金返還といった大きなリスクにつながります。
日常の仕訳を正確に行うこと、帳簿と証憑を常に突合すること、区分経理を徹底すること、そして法人全体で情報を共有すること。こうした積み重ねが、会計業務の負担を減らし、監査対応をスムーズにする近道です。
まずは自園で必要な帳簿を整理し、管理ルールを明確にしましょう。そのうえで、より詳しい実務の流れや効率化の工夫を学びたい方は、収益記事を参考にすることで、具体的な改善策を取り入れることができます。
会計業務を正しく、効率的に行うことは、子どもたちの保育や教育により多くの時間と資源を注ぐための大切な基盤です。今こそ一歩を踏み出し、帳簿管理を園の強みに変えていきましょう。
こちらもCHECK
-

【社会福祉法人会計】保育園、認定こども園におすすめ!クラウド会計ソフトで初心者でも安心して会計の業務負担を削減しよう
社会福祉法人が運営する保育園や認定こども園では、日々の保育に加えて「会計」という大きな仕事があります。子どもたちのこと、職員のこと、保護者対応、行政とのやり取り…。そのうえで、仕分けや帳簿、補助金処理 ...
続きを見る
